医療アクセスの地域格差を埋めるスタートアップ5選

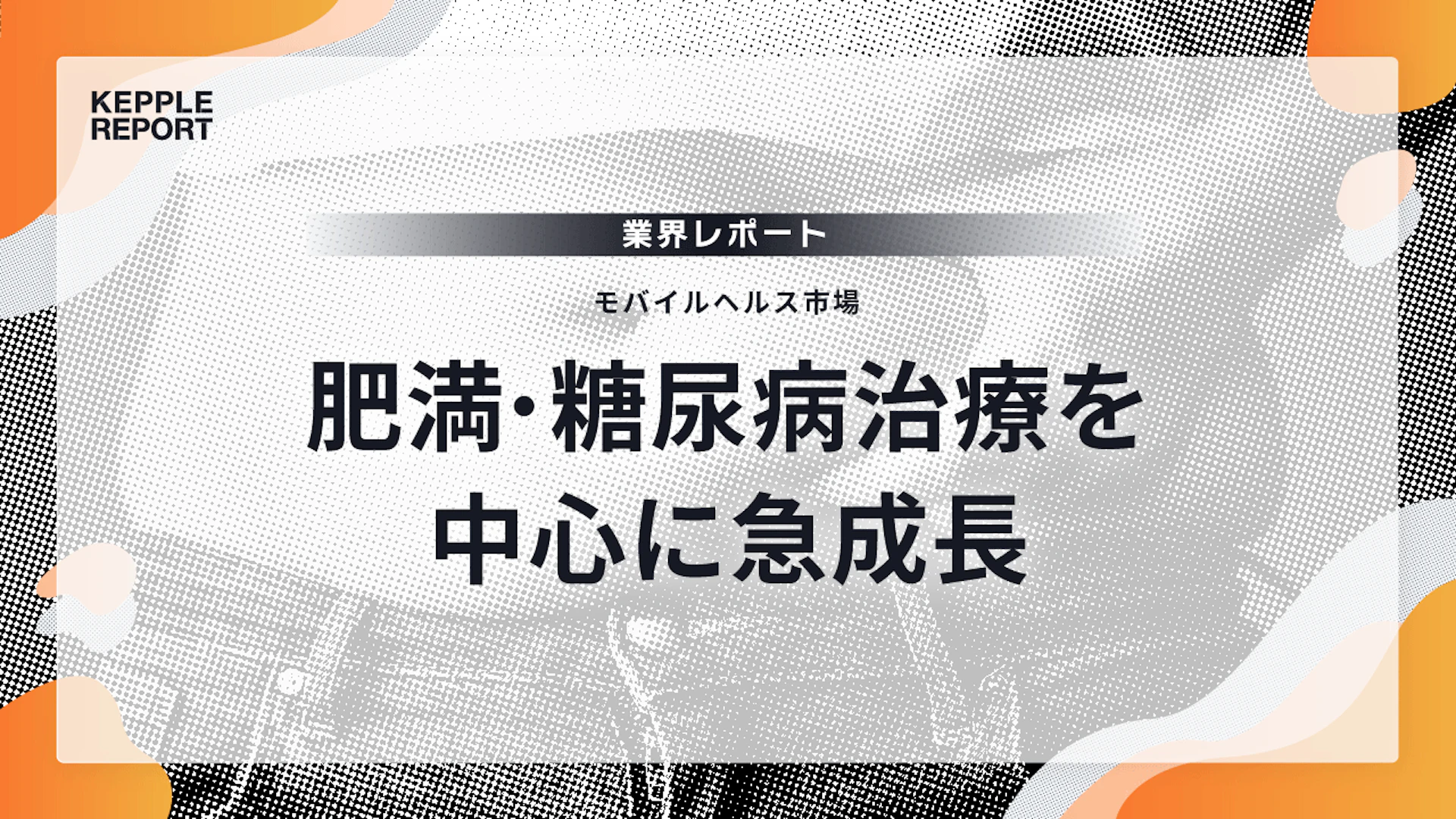
モバイルヘルス(mHealth)は、スマートフォンのアプリなどで提供される医療サービスを指す。
2021年の世界のモバイルヘルス市場は、382億ドルであり、2022年から2030年の間で12%の年平均成長が続くとみられる。
今回は、治療用途の中で最も古くから存在し、サービスを展開する企業が多い肥満/糖尿病治療に焦点をあてる。肥満度が高い程、糖尿病の有病率は高くなる傾向があるため、肥満と糖尿病治療はセットで行われることも多い。Noomなどの海外企業は100万ドル以上調達しており、同市場における投資家の期待値の高さがうかがえる。
今回、業界を理解する上で、インドネシアを拠点とするSirka社のDito Krista氏(COO兼創業者)に取材に応じていただいた。
 Dito Krista氏(COO兼創業者)
Dito Krista氏(COO兼創業者)
大学時代の知り合いであるRifanditto Adhikara氏とDito Krista氏が2021年にSirka社を共同創業した。同社は、Y-Combinatorのアクセラレータープログラムに参加後、AC Ventures、Wavemaker Partners、Sequoia 、Goodwater Capitalなどから2.6百万米ドルのシード調達を行った。
 Rifanditto Adhikara氏(CEO兼創業者)
Rifanditto Adhikara氏(CEO兼創業者)
インドネシアにおけるBMI25以上の成人比率は、20.7%であり、欧米に比べると高くない。日本の同比率は22.4%であり、実は日本の方が高い。ただ、食生活習慣の変化に伴い、肥満人口が増加を続けている。
同社の売上の約6割は、EC上で販売するヘルスケア製品、約4割は減量を中心とした治療アプリのサブスクリプションだという。同社の治療アプリのプログラムを終えたユーザーが割引価格でヘルスケア製品を購入できるなど、2つの事業には大きなシナジーが存在する。
インドのHealthifyMeがインドネシアで積極的に事業展開を行っている。一方、同社の最大の競合は、対面でのサポートを行う栄養士(ほとんどが個人事業主)といえる。
同社は、①対象疾患領域の拡大、②自社ヘルスケア製品の販売、③対象地域拡大による成長戦略を描いている。体重管理は、あらゆる生活習慣病の予防・治療につながるため、対象疾患領域を広げやすい。今後は、2型糖尿病、高血圧に対象疾患領域を広げる予定だ。
日本の糖尿病のデジタル治療は、医薬品・医療機器メーカーがスタートアップと提携する形態が多い。塩野義製薬とAkili(NASDAQ上場、3/1時点の時価総額1.4億ドル)、アステラス製薬とWelldocなどが例として挙げられる。日本のスタートアップとの提携例では、住友ファーマとSave Medical、テルモとMICINがある。
日本では、デジタル投資の遅れや少ない自己負担で受けられる充実した医療制度がモバイルヘルス普及の阻害要因になっていたと考えられる。ただ、膨張する医療費への対応やCOVID-19に伴う非対面・非接触に対するニーズは無視できなくなっている。近い将来、通院せずともアプリ上で治療や予防ができる時代が到来すると考える。
簡単なアンケートにご回答いただくと全文をお読みいただけます
Writer
.png?auto=compress&fm=webp&h=128&w=128&fit=crop)
ケップルアナリストチーム
スタートアップ企業の情報収集・分析を行う専門チーム。ケップル独自のスタートアップデータベース「KEPPLE DB」の構築にも携わっており、KEPPLEメディアやKEPPLE DBへの独自コンテンツの企画、発信を行う。
スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。
1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。
※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします
※配信はいつでも停止できます