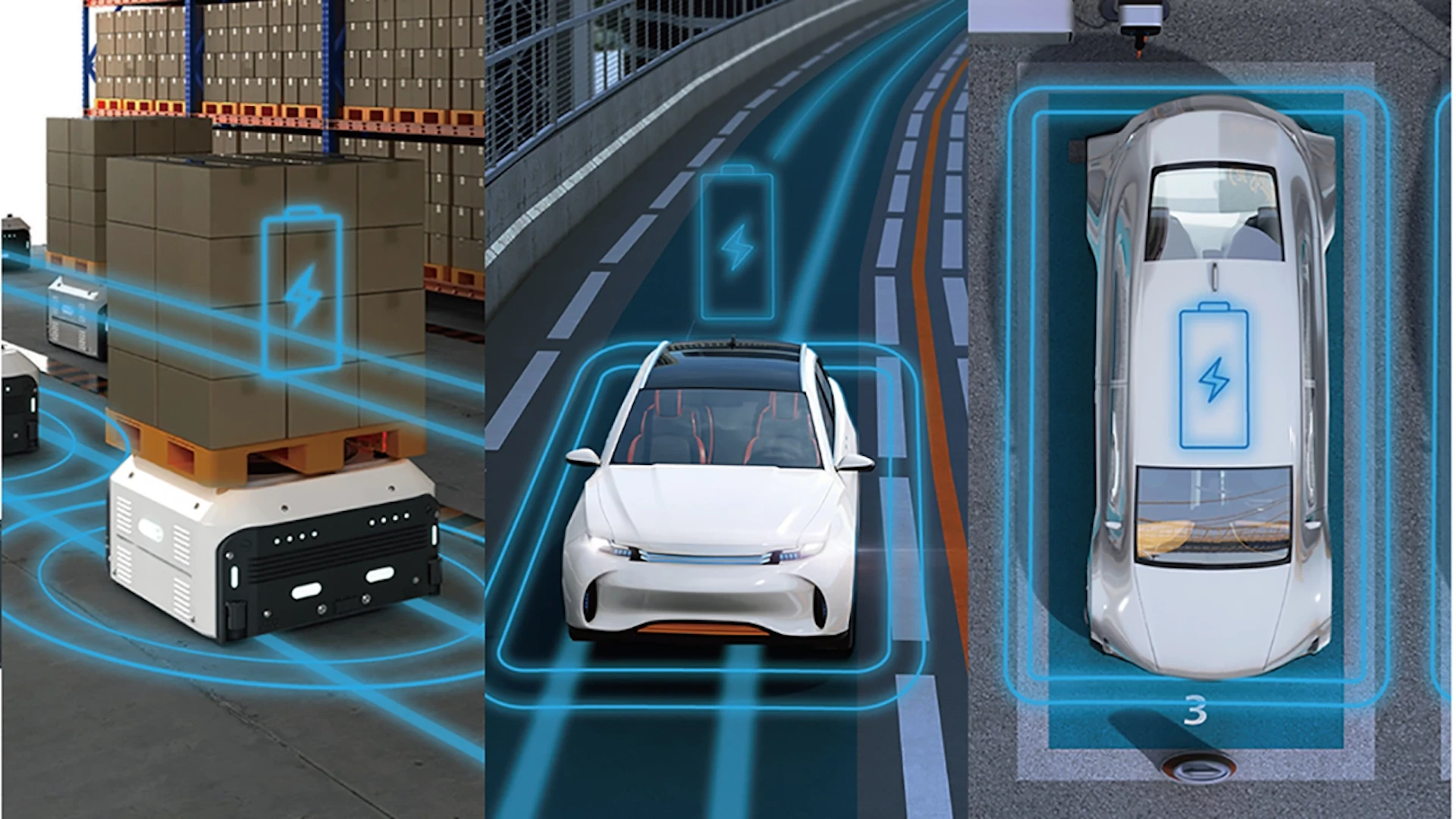Space Aviation株式会社

Space Aviation株式会社は、シリーズBラウンドにおいて総額17.4億円の資金調達を実施したと発表した。累計調達額は約29億円となる。
2019年5月設立のSpace Aviationは、ヘリコプターを活用した旅客輸送、遊覧飛行、防災支援、航空機販売など多角的な航空関連事業を展開している。特徴は、地方と都市を結ぶヘリタクシーサービスや、災害発生時の緊急支援基地としての機能など、交通と防災両方のインフラとして空の活用を志向している点にある。とくに防災・減災では、平時は収益運航、有事はヘリの機動力で山岳救助や広域災害対応に対応できる、公的機関を補完する運用モデルを志向する。全国に9拠点の運航網を構築し、創業から6年で年間売上高36億円を記録。ヘリコプター旅客飛行の取扱実績では国内有数の規模としている。
代表取締役社長の保田晃宏氏は、独立系ファンド運用会社でキャリアをスタートし、不動産投資や中国VCとのジョイントベンチャー投資に従事。その後、事業開発部門の統括としてベンチャー投資や8つの再生可能エネルギーファンドの組成を主導。独立後は航空会社やメーカー、EC企業のファイナンスアドバイザー、CFOとして複数のスタートアップ立ち上げに携わる。2021年にSpace Aviationへ参画し、2022年4月より代表取締役に就任した。
ヘリコプターを含む「空の移動インフラ」は、従来は高コスト・限定的用途にとどまっていた。しかし近年、都市部の交通渋滞や地方の交通網の衰退、自然災害対応などの社会課題を背景に市場環境が変化している。eVTOL(電動垂直離着陸機)など新たなエアモビリティの普及期待も高まるが、運航ノウハウや人材、インフラ整備が普及の障壁となっているのが現状だ。
国土交通省の航空輸送統計によれば、ヘリコプター旅客輸送は2022年度もコロナ禍の影響を受けたが、地域課題解決や観光、防災分野では一定の需要拡大が見られた。一方で、パイロットや整備士の高齢化や人材不足といった構造的課題は深刻化しており、新たな航空人材の育成が急務となっている。国内においては、大手航空会社グループや自治体と連携した運航事業者が競合するが、防災や地方創生を軸に多角的な事業ポートフォリオを構築する例は限られている。
今回の調達では、ZUUターゲットファンド for SA投資事業有限責任組合が16億円、特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)による調達が1.4億円となった。資金は、海外展開に向けたロールアップM&Aの実行資金として活用することを主目的とする。これにより、海外市場の開拓に加え、国内外での航空人材の育成・交流や機体・部品の調達力を強化。さらに、2030年頃に到来が予測される「空飛ぶクルマ」時代を見据え、既存の運航・整備基盤を活かした次世代エアモビリティによる新たな移動インフラの構築を推進する。
Space Aviationは、全国600カ所以上の着陸点を確保し、利便性や運賃低減の鍵となる高稼働率運航体制の構築を進めている。企業によれば、ヘリコプター利用の心理的・経済的ハードルを引き下げ、移動手段の一つとして定着させることが「空のインフラ」普及の突破口になると考えている。予約や搭乗手続きの簡素化、即時対応型の運航モデルなど、新サービス開発にも取り組んでいる。
空の移動手段の一般化に向けて、Space Aviationが既存事業と新たなモビリティとの橋渡しとなる事業基盤をどこまで構築できるかが、今後の動向において重要なポイントとなる。