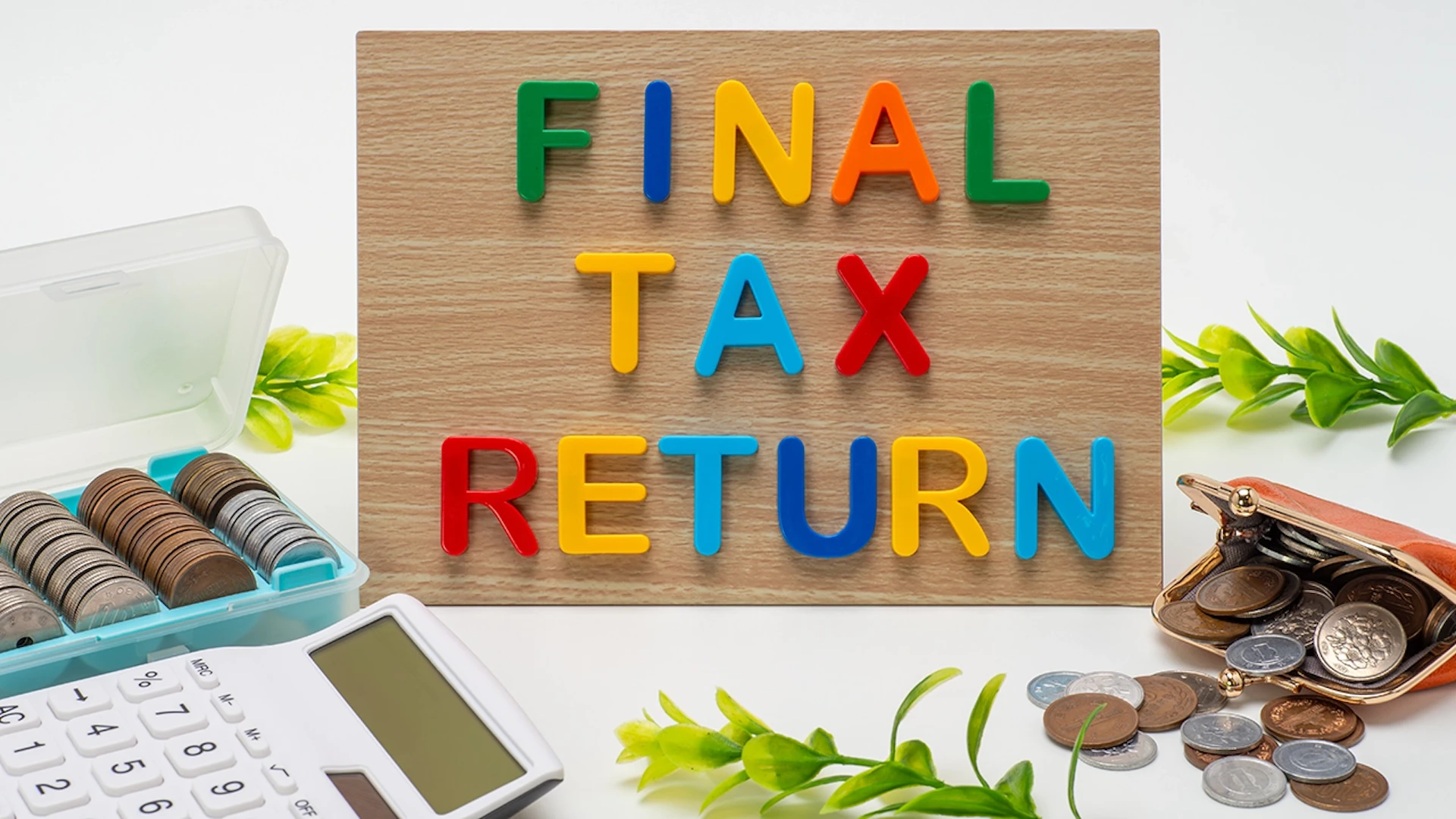株式会社ロケットリンクテクノロジー

宇宙分野への民間参入が拡大する中、小型衛星向けロケットの開発を手がける株式会社ロケットリンクテクノロジーが2025年7月、シリーズBラウンドで5社を引受先とする第三者割当増資により総額6億円の資金調達を実施した。これにより、累計調達額はシリーズAを含めて7.5億円に達した。
ロケットリンクテクノロジーは2023年4月に設立された宇宙スタートアップであり、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の知的財産や研究成果を活用した事業展開を特徴とする。JAXAから「JAXAベンチャー」に認定されており、研究開発拠点との連携体制が整う。事業の中核は、独自開発した「低融点熱可塑性推進薬(LTP)」を用いた固体燃料ロケットだ。このLTPは、従来の固体燃料に比べて製造工程の短縮やリサイクル性の向上を実現するなど、製造・運用コストの低減に寄与する特性を持つ。加えて、教育分野や人材育成、打ち上げや回収方式の研究にも取り組んでいる。
代表取締役社長の森田泰弘氏は、JAXAにてM-Vロケットやイプシロンロケットなどのプロジェクトを歴任し、固体ロケット用燃料の低コスト化や産業応用に向けた研究開発を主導してきた。森田氏は設立者でもあり、共同創業メンバーや幹部陣もJAXAやアカデミア出身者が中心となっている。基礎研究から事業化までの一貫した体制が特徴だ。
世界的に小型衛星の打ち上げ需要は増加の一途をたどっている。地球観測や通信、災害監視など多様な用途により、2023年には世界で約2900基の小型衛星が打ち上げられたとされる。一方、打ち上げ手段は依然として限られており、大型ロケットへの相乗りによる柔軟性の不足や、コスト・リードタイムの課題が指摘されている。国内外ではスペースワンやインターステラテクノロジズといった民間企業が独自の打ち上げサービスの実用化を目指しており、競争が進行中だ。
ロケットリンクテクノロジーが開発するLTPは、従来主流である熱硬化性樹脂(HTPB)と比較して、加熱による融解・充填・再固化が短時間で可能な点が特長だ。一般的な固体燃料の場合、成形から硬化に2〜3週間を要し、精密な工程管理が不可欠だったが、LTPでは最短3日以内で製造が完了する。これにより、従来は難しかった町工場での製造を目指す。これまでに北海道での地上燃焼および飛翔実験により、100mから5kmの弾道飛行を実証。2026年度には高度100km級の実証打ち上げ、2028年以降には小型衛星の軌道投入を想定する開発ロードマップを描いている。
今回のシリーズBラウンドでは、インキュベイトファンド、DIMENSION、住商ベンチャー・パートナーズ、三井住友海上キャピタル、宇宙フロンティア2号投資事業有限責任組合(スパークス・アセット・マネジメントGP)が出資した。
宇宙輸送業界全体では、民間主導型ロケット開発の競争が世界的に加速している。米SpaceXはロケットと衛星事業の垂直統合モデルで成長し、2024年には年間100回超の打ち上げを実施したと推定される。これに対し日本国内市場では、年間数十回規模の高頻度打ち上げや、多品種・小ロットに対応した輸送サービスが求められている。ロケットリンクテクノロジーは、量産に適した独自固体燃料とモジュール設計を採用することで、小型・即応型ロケット市場を狙う構えだ。
さらに、ロケット技術の教育・人材育成分野にも力を入れている。教育機関と連携した実験用超小型ロケットの開発や、組み立て体験などの教材用途としての事例もあり、今後の需要拡大も見込まれる。小型ロケット開発の技術が教育現場にも波及しつつある状況だ。
今回調達した資金は実証機の開発、飛行試験、量産技術の開発、人材拡充や事業基盤の強化に充てられる予定である。2026年度のLTP-310飛行試験と、2028年以降の軌道投入型ロケット開発を開発目標として掲げている。小型衛星をはじめとする新たな宇宙利用が拡大する中、低コストかつ即応性の高いロケット開発の進展が日本の民間宇宙産業全体にも影響を及ぼす可能性がある。
宇宙輸送ビジネスの競争激化や法制度の整備、産業基盤の構築などを背景に、ロケットリンクテクノロジーは今後も独自技術を軸に事業を展開していくことが見込まれる。