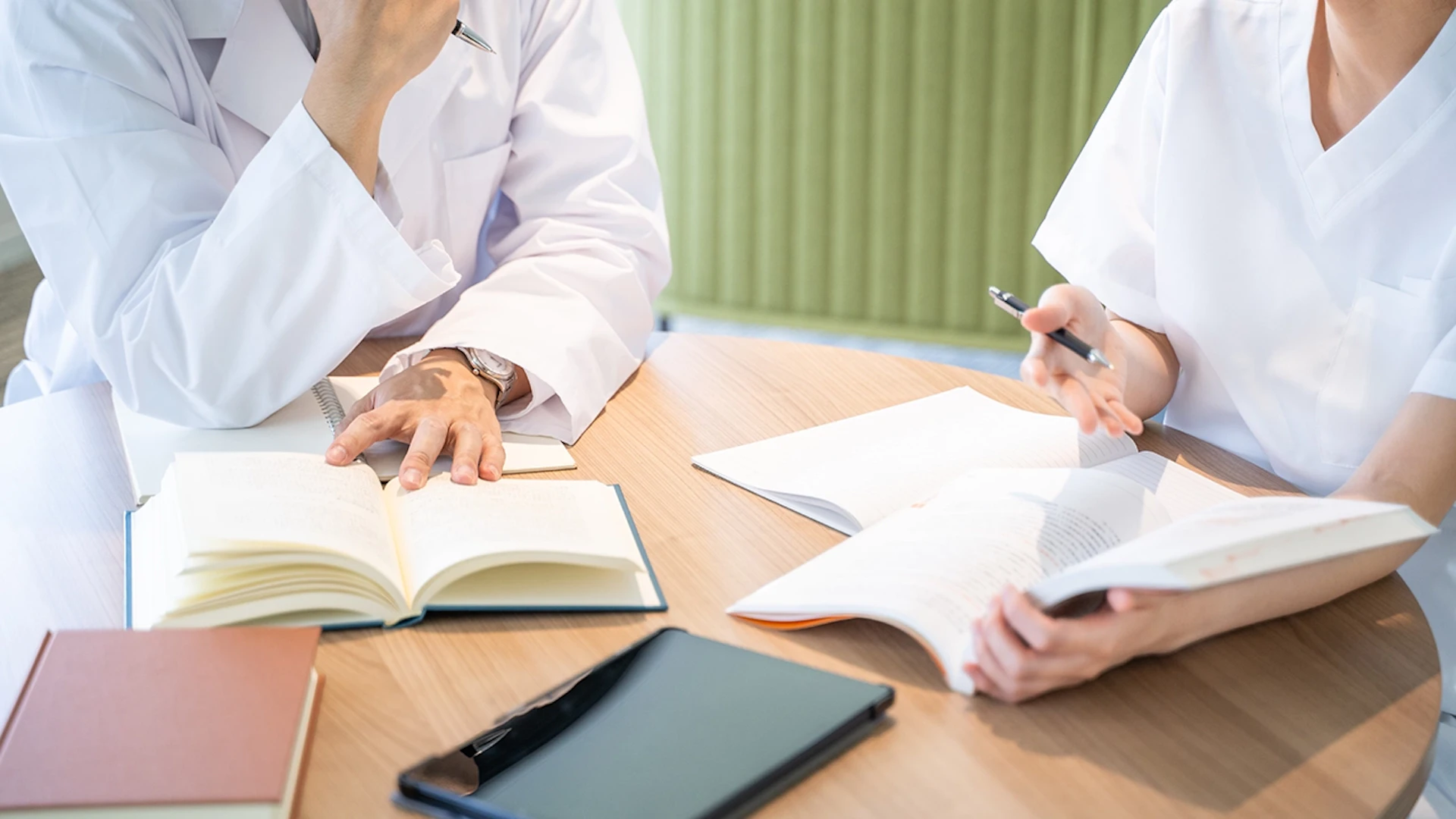株式会社MJOLNIR SPACEWORKS

株式会社MJOLNIR SPACEWORKSが、シリーズA+ラウンドで第三者割当増資による総額4億円の資金調達を実施した。引受先はIncubate Fund、UntroD Capital Japan、三菱UFJキャピタルであり、これにより累計調達額は8.5億円となった。
MJOLNIR SPACEWORKSは2020年1月に設立された宇宙関連スタートアップで、ハイブリッドロケットエンジンと無溶接燃料タンクの開発・量産に注力している。宇宙産業では、打ち上げ需要の増加に対して機数不足とコスト高が慢性的課題となっており、同社は「安全性・低コスト・高頻度」を実現するロケットエンジンの大量生産体制を構築し、市場のボトルネック解消に取り組んでいる。
開発中のハイブリッドロケットエンジンは、固体燃料と液体酸化剤を組み合わせる推進方式を採用しており、プラスチック系燃料の導入により爆発リスクを抑え、安全性の高い設計が特徴だ。2024年11月と翌年5月には40kN級の大型エンジンで地上燃焼試験に成功し、商用規模クラスの推力を確認した。加えて、宇宙用燃料タンクは溶接を使わない一体成形技術による「無溶接タンク」を開発しており、短納期かつ低コストでの量産に適している。
代表取締役のTor Viscor氏は、創業以来経営を主導してきた。開発チームには研究者や技術者、生産管理担当が在籍し、札幌を拠点に東京・川崎など複数の拠点を活用してエンジン開発・試験に取り組んでいる。
宇宙輸送市場では近年、民間主導の新興企業が「NewSpace」として台頭し、小型・中型衛星の打ち上げ需要拡大を背景に市場規模が成長している。世界の宇宙推進機産業は数十億ドル規模に達し、今後も成長が見込まれている。国内市場ではインターステラテクノロジズ、Letara、AstroXなどのベンチャーが競合している。
ロケット打ち上げ用エンジンは一般に液体燃料型が主流であり、SpaceX(Raptor)や三菱重工(H3ロケットLE-9)などが開発・製造している。一方で液体燃料型は構造が複雑でコスト・納期の面で課題がある。対するハイブリッド型は構造が比較的シンプルで量産に適し、安全性が高いとされるが、大型化や燃焼安定性、再点火といった技術的課題も多く、世界的にも実用化例は限られている。米国bluShift Aerospaceや神奈川大学なども開発を進めているが、依然として参入企業は少数にとどまる。
累計8.5億円の資金調達は、国内宇宙スタートアップの中でも存在感のある水準となる。今回の調達資金は、ハイブリッドロケットエンジンおよび宇宙用無溶接燃料タンクの高度化、人材採用の強化、海外展開の加速に活用される予定だ。
北海道では宇宙関連スタートアップの活動が札幌や大樹町を中心に進展しており、自治体や大学との産学連携も活発化している。欧米企業が高いシェアを持つ中、国内でも技術基盤や生産体制の強化が進められている。
今後、宇宙輸送市場の競争が激化する中で、技術特化型スタートアップが事業規模拡大と安定供給体制の確立をどのように進めるかが課題となる。エンジンや燃料タンクなど中核部品の量産と信頼性向上、顧客基盤の拡大が宇宙産業成長の要素であるといえる。