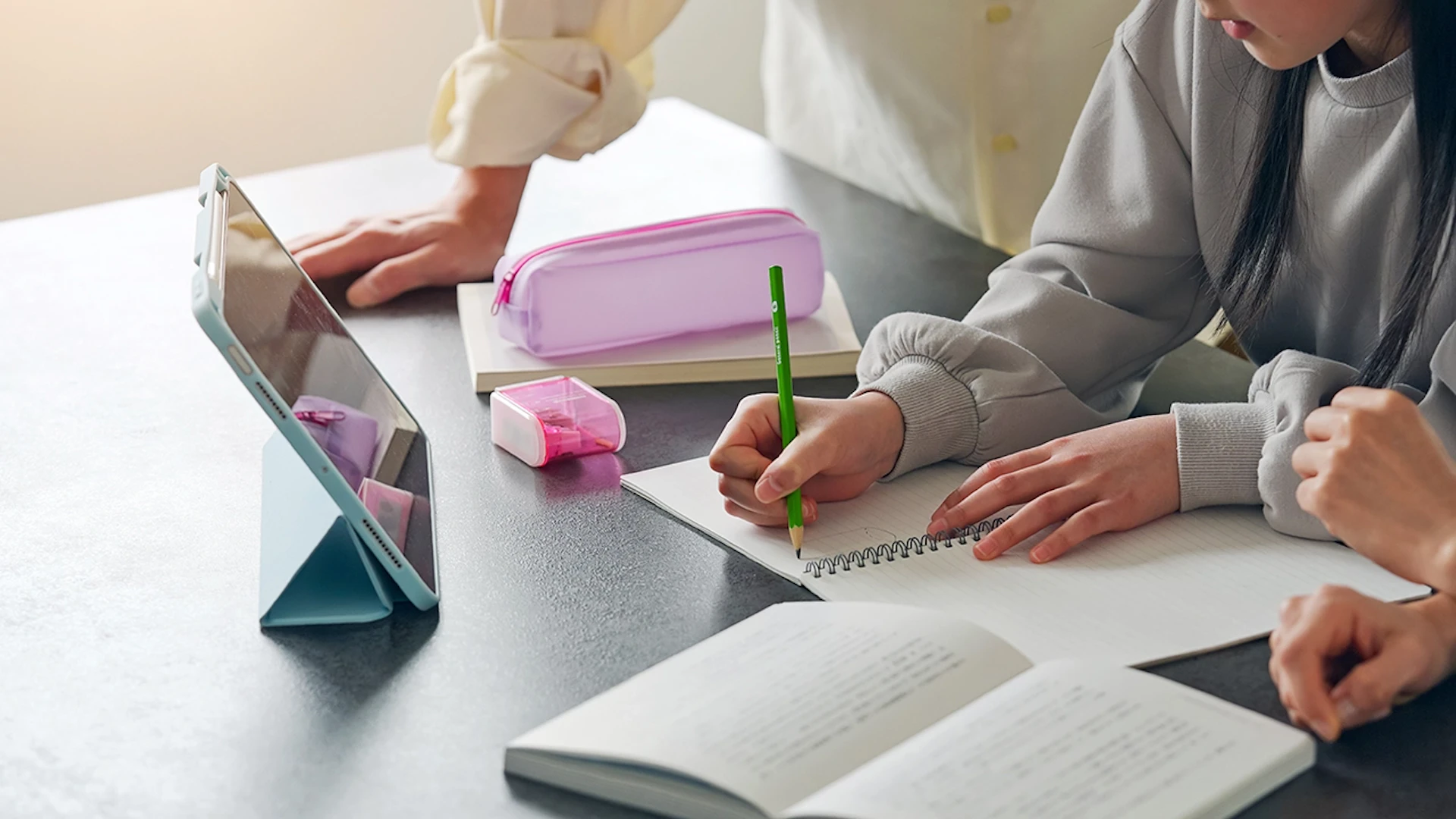AI-DataScience株式会社

AI/SaaSを企画・開発するAI-DataScience株式会社が、医療系エンジェル投資家やVCなどから6000万円の追加調達を実施し、累計約1億円の資金調達を完了したと発表した。
AI-DataScienceは2023年11月設立。AIやデータサイエンスを基盤とするSaaS(Software as a Service)の企画・開発を主軸事業とする。医療、物流、コールセンターなど、いわゆる「しんどい業務」の解消を目指したAIエージェントの開発に取り組み、業務構造や現場課題に即した共創型AIモデルの事業化を推進している。SaaS開発では、現場ニーズの把握からプロダクト設計、導入、改善までを効率的に実施し、複数の企画を並行展開するフレームワークを採用している。医療AI「Curalumi®」のほか、業務効率化を支援するAI電話システムなど、多分野でソリューションの幅を広げていることが特徴だ。
代表取締役の倉橋一成氏は、医療データサイエンス領域での経験を経て、2011年にコンサルティング会社を設立。ドコモやリクルートなどの大手企業で利益改善を支援した実績を持つ。アート分野にも関わり、英国王立美術家協会の名誉会員を歴任した経歴を有する。経営、アート、データサイエンスの知見を融合し、2023年にAI-DataScienceを創業した。
DXやAI導入の重要性が高まる一方、日本国内ではプロジェクトの停滞や現場定着の難しさが指摘されている。経済産業省「DXレポート2」では2020年10月時点での回答企業約500社におけるDX推進への取組状況を分析した結果、実に全体の9割以上の企業がDXに全く取り組めていない、あるいは散発的な実施に止まっている状況であるとされている。また、厚生労働省では、医療分野におけるデジタル化を推進している。診療の効率化や医療機関の業務負担軽減を目的とし、電子処方箋の導入や標準型電子カルテシステムの開発、介護情報基盤の構築などが進められている。
こうした業界背景を受け、AI-DataScienceは主力プロダクトである診断前問診AI「Curalumi」の国内外展開を資金使途の中心に据える。Curalumiは、患者がスマートフォンからAIに症状を相談し、診断候補や問診内容が医師に共有される診察支援エージェントだ。アプリのインストール不要でQRコードから利用できる仕組みを持つ。フランスの医療機関で導入された事例では、2時間で患者15人の診察が可能となり、導入前と比べて処理効率が2倍になったとされる。国内でも多診療科クリニックなどで導入が進みつつある。
今回の資金調達により「Curalumi」以外にも、各業界向けAI共創プロジェクトの推進、エンジニアやプロダクトマネージャーの採用強化、セキュリティ基盤の整備、PoC導入活動の加速などが計画されている。とくに業種ごとに1社限定で協業する「業界別AI共創モデル」によって、個別最適化されたAIの開発と外販事業の拡大を目指す。物流、コールセンター、人材領域などで複数のプロジェクトが進行中とされる。知財戦略ではAI関連で4件の特許を取得済みであり、知財活用による競争優位の確立にも取り組んでいる。
同分野にはJDSCなどが産学官連携型・社会基盤系のAI開発を行い、大手SIerやコンサルティング企業が業務効率化サービスを展開している。AI-DataScienceは現場課題からのボトムアップ型設計と共創プロセスを重視しており、既存大手が大規模・汎用型ソリューションを提供するのに対し、業界別特化型のパートナーシップや短期間開発、高速な市場投入を特徴とする。
今後は「Curalumi」の国内展開拡大、業界別AI開発パートナーの増強、採用強化、海外(欧州・ASEAN)での事業調査・連携などが計画されている。資金・人材・技術基盤の拡充を通じて、現場課題に根差したAIプロダクトの事業化と市場展開を進める方針だ。
画像はAI-DataScience HPより