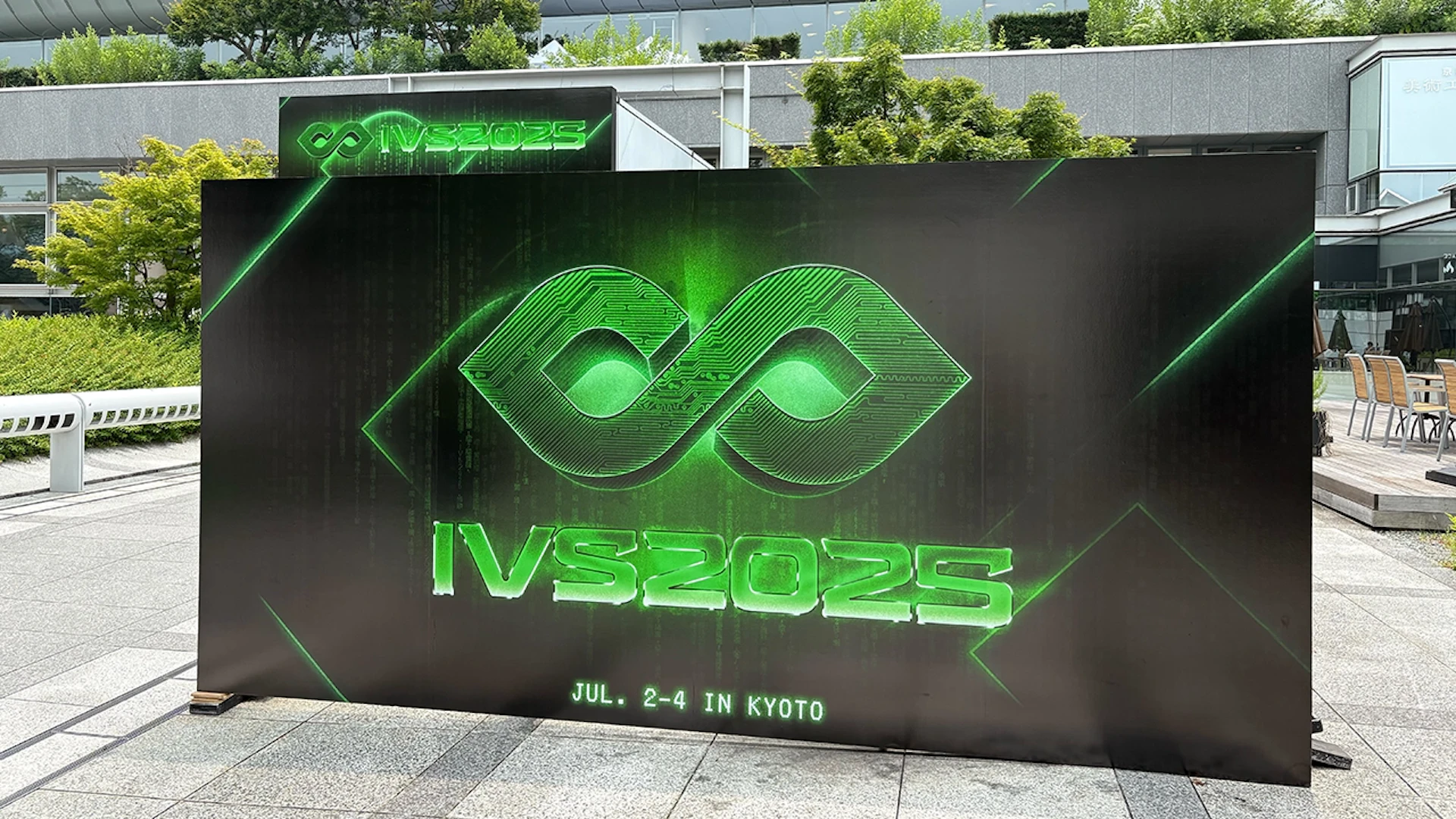ASTRA FOOD PLAN株式会社

目次
インパクトスタートアップ協会(ISA)が主催する「IMPACT STARTUP SUMMIT 2025」が、2025年10月14日(火)、東京コンベンションホール(京橋)にて開催された。
今年のテーマは「Impact Showcase - 社会課題解決の見本市」。政官財学の各界からリーダーやスタートアップが一堂に会し、社会課題に挑む最新事例や制度動向について議論が交わされた。
社会的課題の解決と経済的リターンの両立を目指す「インパクト投資」の国内市場は、2024年時点で17兆円を超える規模に拡大。こうした流れの中、ISAの正会員数も250社に達し、社会課題解決型ビジネスのエコシステムが加速している。
本イベントはインパクトエコシステムの「今」と「これから」を示す重要な節目として注目を集めた。
現場から始まる社会変革とインパクト経営の可能性
イベント冒頭では、インパクトスタートアップ協会 代表理事であり、READYFOR株式会社 代表取締役CEOの米良はるか氏が登壇。開会の挨拶として、本サミットの開催意図と、いま社会に求められているスタートアップのあり方について語った。
米良氏は、NPOや地域団体と連携し、寄付や支援が単なるお金の移動ではなく、「想いの乗ったお金」が「想いのある現場」へ届くことの意義を強調。単なる仕組みではなく、現場のリアリティに根ざしたインパクト創出の重要性を示した。
スタートアップと官民共創で築く新しい資本主義
基調講演には、前内閣総理大臣の岸田文雄氏が登壇。インパクトスタートアップを核とした新しい資本主義の展望について、自らの政策的取り組みを交えて語った。
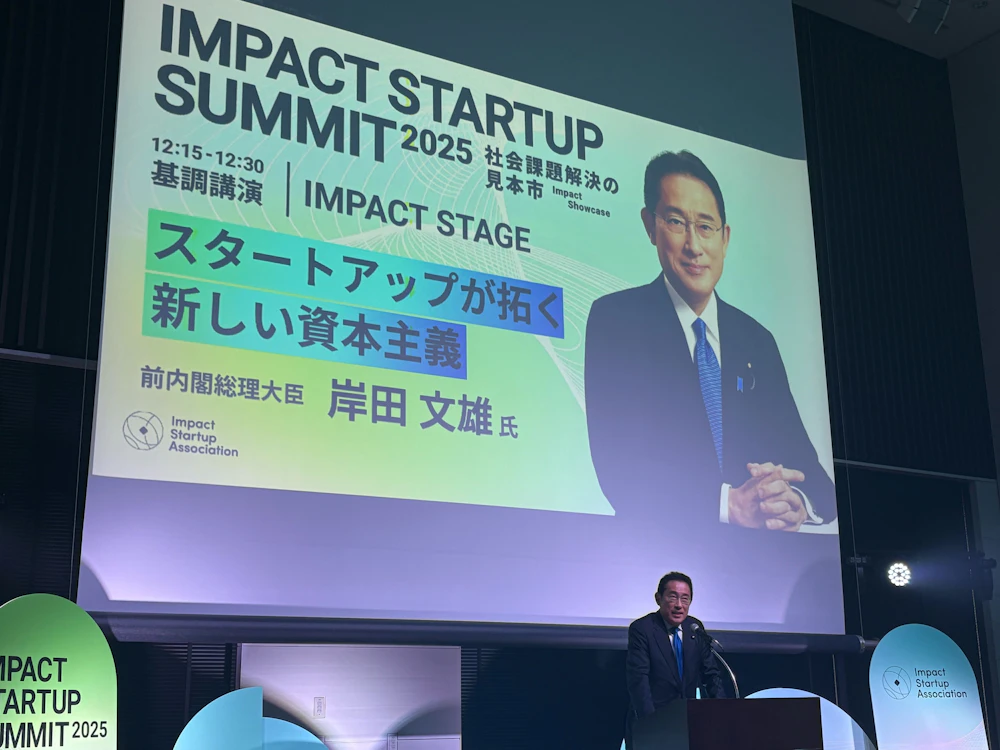
岸田氏は、2022年をスタートアップ創出元年と位置づけ、新しい資本主義実現会議に米良はるか氏を招くなど、官民対話を重ねてきた経緯を紹介。その上で「スタートアップ育成5カ年計画」を策定し、人材・資金・オープンイノベーション推進の3つの柱で環境整備を進めてきたと振り返った。
その成果として、スタートアップ数は2021年の1万6千社から2万5千社超へ、大学発スタートアップも3300社から5000社超に増加。インパクトスタートアップ協会の会員数も設立当初の23社から10倍以上に拡大したことを明かした。
また、産官学・金融界など幅広い関係者が協働・対話を行う場として「インパクトコンソーシアム」が設立されたことにも言及。インパクトの測定管理に活用できる実践的なデータ・指標の整備や、地方自治体とインパクトスタートアップの連携に向けた検討が進められていることを紹介した。
社会性と事業性を両立しながら社会課題に挑むスタートアップこそ、資本主義の未来を担う存在である──そうした静かな確信とともに、インパクトスタートアップへの期待をにじませた講演となった。
IMPACT STARTUP PITCH、未来のインパクトリーダー10社が競演
当サミットの目玉でもある「IMPACT STARTUP PITCH」。ISA正会員の中から選ばれた、創業5年以内のアーリーフェーズのスタートアップ10社が登壇し、熱のこもったピッチを繰り広げた。
また、本ピッチには、ISA賛同会員の大企業から構成される審査員団が参加し、「インパクトスタートアップピッチ大賞」をはじめとする計10の賞が授与された。
今年は社会構造の変革、環境課題への挑戦、地方創生や家族の在り方まで、多様な領域にわたる社会課題に対して、テクノロジーやユニークなアプローチで立ち向かうスタートアップが集結。 会場は終始、登壇者と聴衆の熱気と共感に包まれた。
スタートアップピッチ 各賞受賞結果
インパクトスタートアップピッチ大賞
受賞企業:ASTRA FOOD PLAN株式会社(代表取締役 加納 千裕氏)
2025年のインパクトスタートアップピッチ大賞に選ばれたのは、「隠れフードロス」に取り組むASTRA FOOD PLAN株式会社。食品工場で廃棄される野菜の端材やジュースの搾りかすを、独自の乾燥技術で香り高い食品パウダーへとアップサイクルする事業を展開している。

吉野家との協業による玉ねぎパウダーの開発実績や、B2B・B2Cの双方で循環型モデルを構築している点が評価され、審査員の総合得点で最高位を獲得した。
さらにASTRA FOOD PLANは、来場者のリアルタイム投票による「オーディエンス賞」、野村證券株式会社による「野村賞」も受賞。審査員と観客の双方から圧倒的な支持を集めた。
審査員である丸井グループの遠藤真見氏は「製品の香りに震えた。共感と応援の気持ちが票に表れた結果だ」と述べ、野村證券の鳥海智絵氏も「農業・廃棄物削減・ブランディングの融合という新しい挑戦に強く共感した」と評価した。
三冠を達成した加納氏は、「驚きと感謝でいっぱいです。アップサイクル市場は未成熟だが、“おいしい”で循環を完了させたい。これからも循環型社会の実現に向けて事業を伸ばしていきたい」と意気込みを語った。
みずほ賞 & 三井住友信託銀行賞
受賞企業:エイターリンク株式会社(代表取締役CEO 岩佐凌氏)
ワイヤレス電力伝送を軸に、スマートビルや物流など多分野で応用可能な技術を展開するエイターリンク株式会社が、「みずほ賞」「三井住友信託銀行賞」をダブル受賞。

みずほ銀行の金田真人氏は「いよいよ量産・スケールのフェーズに入った。ここからが次のステージ」と述べ、三井住友信託銀行の加茂道敬氏も「不動産の価値向上につながる技術。今後の連携にも期待したい」と語り、成長段階に入った同社の展望に期待を寄せた。
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー賞
受賞企業:株式会社MEMORY LAB(代表取締役 畑瀬研斗氏)
東京建物YNK賞
受賞企業:スコレ株式会社(代表取締役 須藤奨氏)
三井住友フィナンシャルグループ賞
受賞企業:株式会社My Fit(代表取締役 山田真愛氏)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券賞
受賞企業:株式会社すきだよ(代表取締役 熱田 優香氏)
東海東京証券賞
受賞企業:株式会社JOYCLE(代表取締役 小柳 裕太郎氏)
その他の登壇企業一覧(順不同・敬称略)
SORA Technology株式会社(Founder/CEO 金子洋介氏)
株式会社Piezo Sonic(代表取締役 多田興平氏)
株式会社LivCo(CEO 佐々翔太郎氏)
「インパクト・チャレンジ・オブ・ザ・イヤー」受賞3社に見る未来のかたち
続いて、公式プログラムの一つとして、Forbes JAPAN主催のピッチイベント「IMPACT CHALLENGE OF THE YEAR 2025」が開催された。
この取り組みは、インパクトスタートアップ協会との共催により、「挑戦を称え、応援する」をコンセプトに、経済性だけでなく社会的インパクトを軸に企業を評価する新たなムーブメントを生み出すものだ。
初開催となった今回は、インパクトスタートアップ協会の正会員250社の中から、ミドル〜レイターフェーズにあり、かつ社会課題への独自のアプローチと成長可能性を併せ持つ6社がノミネート。
当日のプレゼンテーションと会場投票を経て、3社が受賞企業として選出された。

受賞企業(敬称略・順不同)
リージョナルフィッシュ株式会社(代表取締役社長 梅川 忠典)
地球沸騰化とも称される水温上昇に対し、ゲノム編集と完全養殖を組み合わせて「高温耐性魚種」の開発を推進。地方の名産魚を未来に残す革新的な技術と地域経済への貢献が高く評価された。
株式会社HAKKI GROUP(代表取締役 小林 嶺司)
アフリカでの中古車ローン提供を通じ、タクシードライバーの職業機会を創出。金融包摂と交通インフラの課題を同時に解決する、スケーラブルかつ社会性の高いマイクロファイナンス事業が注目を集めた。
株式会社Luup(代表取締役CEO 岡井 大輝)
都市部・地方問わず利用可能な小型電動モビリティの開発を推進。開発を進めている“横転しない3輪モビリティ”を発表し、高齢者や免許返納者の移動手段としての実装可能性が大きなインパクトを示した。
その他のノミネート企業 ※以下、登壇者敬称略、順不同
アスエネ株式会社(Founder & 代表取締役CEO 西和田 浩平)
SHE株式会社(代表取締役CEO・CCO 福田 恵里)
株式会社ユカリア(代表取締役社長 三沢 英生)
高市早苗氏が語る「日本を支えるのはスタートアップの力」
特別講演には、自由民主党 総裁の高市早苗氏が登壇。「日本列島を強く、豊かに」という演題のもと、自身の原点からスタートアップへの期待までを語った。
高市氏は、松下政経塾時代に松下幸之助氏から受けた「成功の予定は成功するまで続けるところにある」という教えが、政治家を志すきっかけになったと振り返った。リーダーシップについては、「責任は自分が取る」「より良い方法があれば変える勇気を持つ」という姿勢を、総務大臣を史上最長の約4年間務めた経験も交えて語った。

中盤では、宇宙ゴミ除去を手がけるアストロスケールホールディングス社の取り組みに言及。「世界が注目する日本の技術が、外交や安全保障にも貢献している」とし、G7会合での議題化の背景にも触れた。
最後に、「社会課題の解決に挑むスタートアップは、日本を成長させる原動力」と述べ、緊縮財政ではなく国が呼び水として投資し、技術の社会実装や海外展開を後押しする必要性を訴えた。
次なる1000社へ、インパクトの連鎖を
イベントの最後を飾ったクロージングセッションでは、インパクトスタートアップ協会の理事たちが登壇。理事に新たに加わった株式会社カケハシ代表の中尾 豊氏は「インパクトと経済性は必ずしも同時に成果が出るわけではないが、それでも挑戦を続ける意義をこの場で確信できた」と述べ、スタートアップの“滑走路”としての協会の存在価値を強調した。

創業期から協会を牽引してきた星直人氏は、「グローバルにも類を見ないこのコミュニティが、日本発でインパクトの潮流を牽引すべき」と呼びかけ、「志を下げることなく、共に未来をつくっていこう」と締めくくった。
代表理事の米良はるか氏も、「挑戦を続ける仲間と出会えたこの場が、明日への力になる」と語り、社会課題の解決と経済性の両立を目指すスタートアップコミュニティの拡大を改めて呼びかけた。