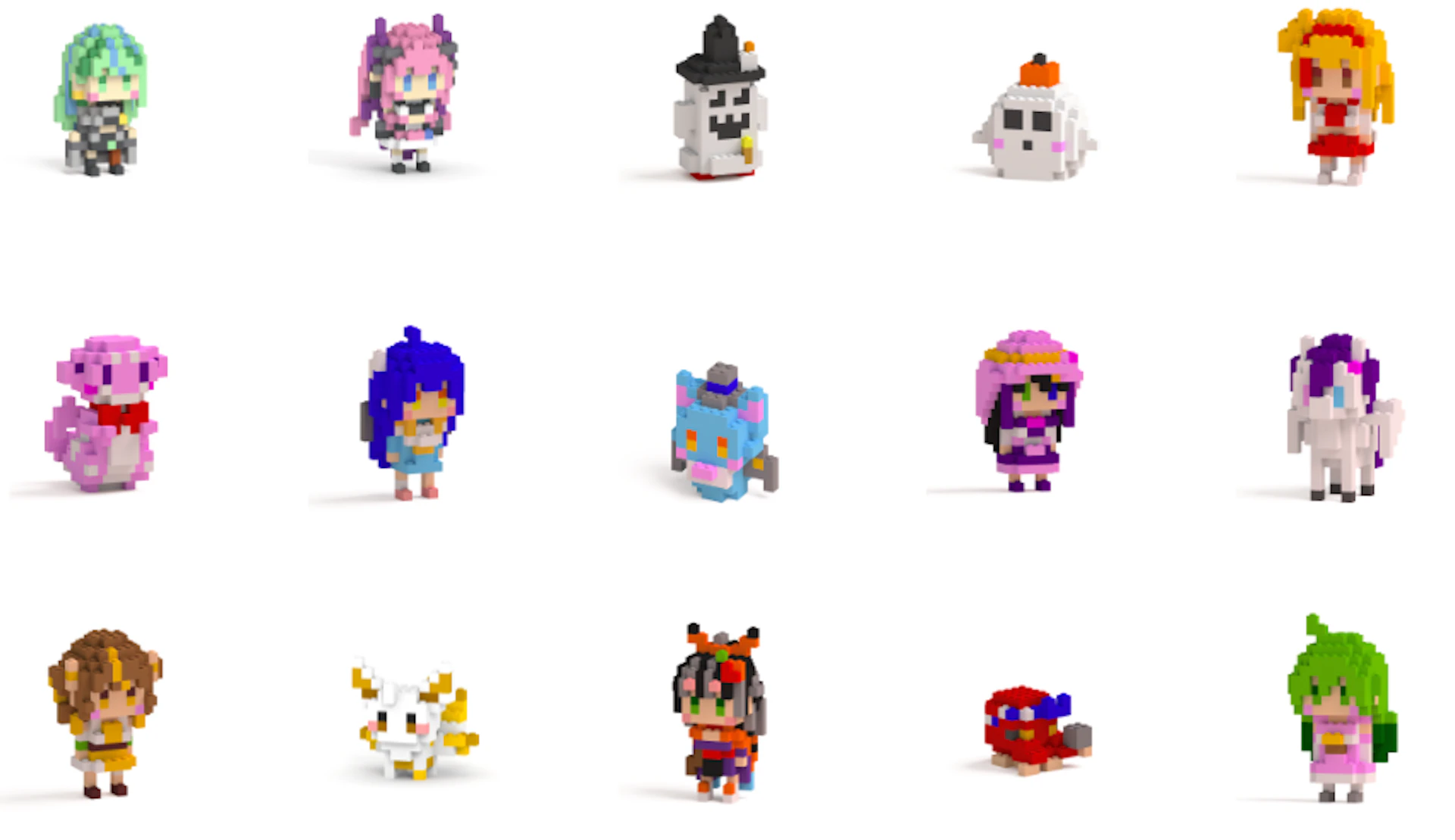株式会社ロボトラック

株式会社ロボトラックがプレシリーズAラウンドで約12億円の資金調達を実施した。調達資金は自動運転トラックの社会実装に向けた技術開発や実証実験の拡大、経営体制の強化などに充てられる見通しだ。
日本の物流業界は、いわゆる「2024年問題」と呼ばれるトラックドライバーの時間外労働規制強化に直面している。これにより輸送力の低下や人手不足が顕在化し、業界全体で自動運転トラックの導入が期待されている。自動運転技術の社会実装は、労働力不足の解消だけでなく、物流サービスの効率化や安全性の向上、さらには脱炭素化の流れにも合致するものと位置づけられている。
ロボトラックは2024年設立のスタートアップで、大型トラック向けの自動運転システムの研究開発と社会実装を主な事業領域としている。独自に開発したAIアルゴリズムを活用し、完全無人運転を目指した技術開発を進めていることが特徴だ。国内では2025年度に東京-名古屋間、2026年度に東京-大阪間でレベル4相当の走行実証を予定し、2028年度以降の製品提供を計画している。
同社の創業者であり取締役を務めるナン・ウー氏は、米国において大型トラック自動運転スタートアップであるTusimpleの共同創業者として世界初のレベル4自動運転トラックの開発やナスダック上場を主導した経歴を持つ。2024年よりロボトラックの創業に参画し、日本の物流課題に取り組む体制を築いてきた。2025年6月には、羽賀雄介氏が代表取締役CEO(共同創業者)に就任。羽賀氏は商社や自動車メーカー、スタートアップ(SkyDrive COO)などでモビリティ分野の多様な実務経験を積んでおり、経営と事業開発の両面で組織をリードする。
物流・自動運転分野では、国土交通省の試算によれば2030年にはトラック輸送の約3分の1が人手不足によって担えなくなるとされる。自動運転技術の導入は、こうした構造的課題への対応策として注目されている。政府も貨物専用の自動走行道路構想を進めており、幹線輸送における自動運転実証の動きが加速している。国内の競合には、TierIV、T2、いすゞ、三菱ふそうなどの大手やスタートアップがあるが、完全無人の長距離運用や高度な技術人材の獲得に取り組む企業は限られている。
資金調達の経緯としては、2025年3月に東大IPC、PKSHA Algorithm Fund、AIS Capitalからシードラウンドで3億円を調達。今回のラウンドでは、グロービス・キャピタル・パートナーズがリード投資家となり、オリックス、Archetype Ventures、Mizuho Leaguer Investmentなどが新規投資家として参画。既存投資家からの追加出資も含め、約12億円を調達した。
調達した資金は、技術開発体制の強化、長距離実証実験の拡大、インフラ企業との連携強化、営業体制の増強などに充てられる。なお、オリックスとの間では資本業務提携を締結し、車両提供や事業化検証も進める方針だ。
ロボトラックが開発中の自動運転システムは、AIによる認知・判断統合、VLMなど、複数の先端技術を組み合わせている。直近では新東名高速道路において100kmのレベル4相当走行テストを完了しており、今後は段階的にテスト区間の延長や完全無人化を目指すとしている。
自動運転トラック分野は、効率的かつ持続可能な物流サービス、運行の安全性向上、労働力不足への対応、脱炭素化やサプライチェーンの事業継続性(BCP)強化といった複数の社会的ニーズに応える領域である。一方で、既存車両メーカーや関連事業者との競合、規制適合や社会的受容性といった課題も根強い。現在は限定区間や夜間走行などから段階的な社会実装が進行しており、今後はビジネスモデルや運用責任の明確化も求められる。
ロボトラックは、今後も投資家やパートナー企業と連携し、日本の幹線物流向け自動運転トラックの実用化と商業展開に取り組む計画である。2028年度の自社システム提供開始を目指し、技術開発や実証フィールドの拡大、パートナーとの事業連携を強化していく構えだ。
代表者情報としては、代表取締役CEOの羽賀雄介氏は共同創業者であり、モビリティ分野における豊富な実務経験を持つ。創業者で取締役のナン・ウー氏は、米国で自動運転技術のスタートアップを共同創業し、世界初の大型トラック自動運転の商用化を主導した経歴を有する。
自動運転トラック分野における今後の事業展開は、業界内外から注目が集まっている。