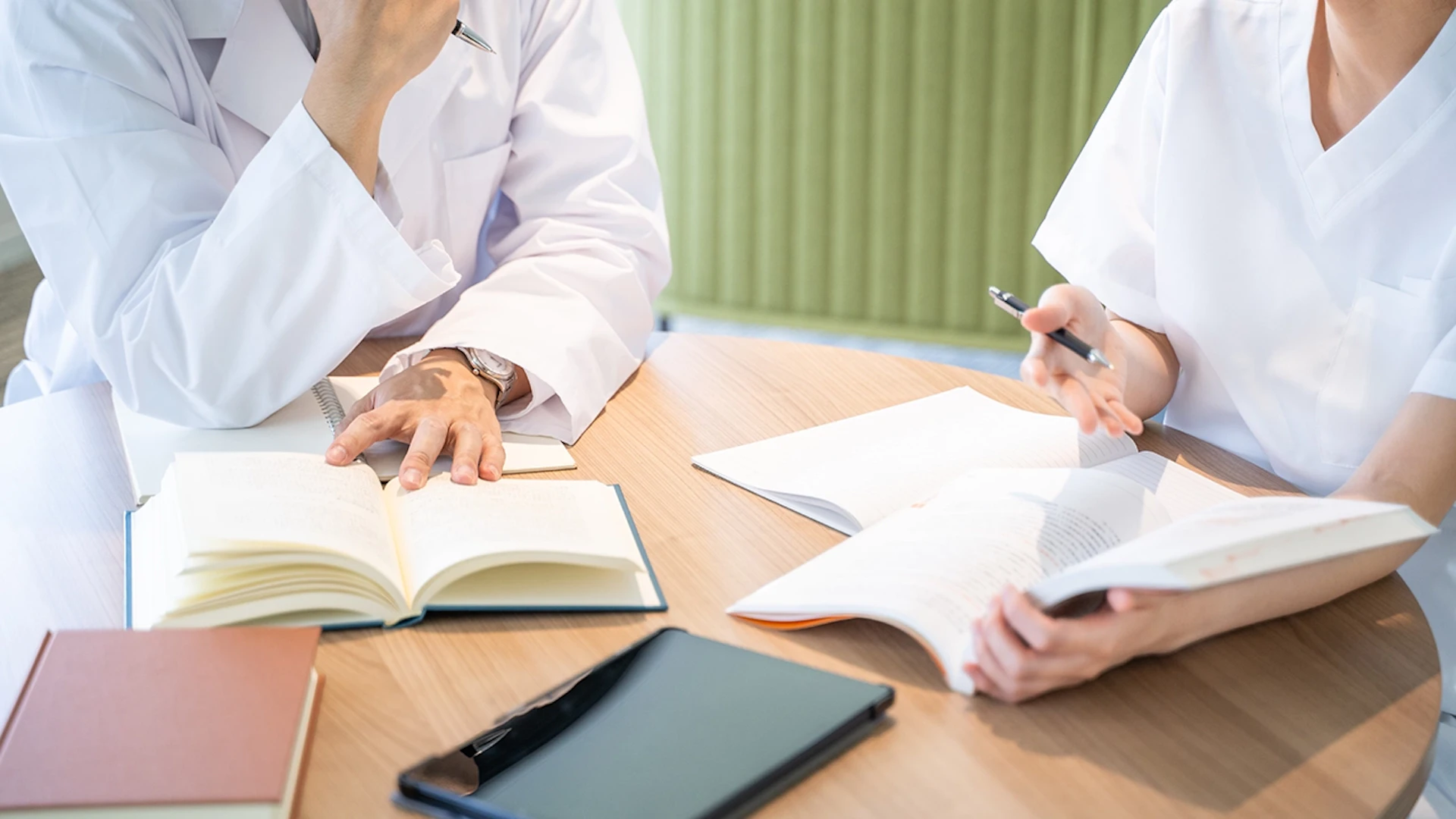株式会社ロボトラック

自動運転トラックの実用化に取り組むスタートアップ、株式会社ロボトラックが2025年9月までに累計16.5億円の資金調達を完了した。今回のラウンドではJICベンチャー・グロース・インベストメンツとSMBCベンチャーキャピタルが新たに出資した。
ロボトラックは2024年4月設立のスタートアップで、大型トラック専用の自動運転技術およびその実用化ソリューションの開発を手がけている。独自のAIアルゴリズムや冗長化構成、安全性と耐環境性を意識した走行制御技術、高精度センサーを組み合わせ、完全無人運転の実現を目指している。設立から1年以内に、経済産業省のモビリティDX支援事業に採択され、新東名高速道路の一部区間(駿河湾沼津SA~浜松SA間、約100km)でレベル4相当の自動運転テスト走行を達成した。今後は東京―名古屋間(約300km)、さらに2026年には東京―大阪間(約600km)での長距離実証実験へと拡大する計画だ。
代表取締役CEOの羽賀雄介氏。2025年6月、羽賀雄介が共同創業者として代表取締役CEOに就任。慶應義塾大学卒業後、三菱商事に入社し、自動車事業でいすゞ自動車の東南アジア向け営業・マーケティングを担当。帰国後は宇宙航空事業にて中央省庁向け新規事業開発や大手企業とのJV設立、スタートアップ投資案件に携わった。その後、SkyDriveでCOOとして空飛ぶクルマやドローン事業を統括してきた。共同創業者で技術開発責任者のNan Wu氏は、米国自動運転スタートアップTusimpleの共同創業者として知られ、2016年から世界初のレベル4自動運転大型トラックの開発を主導した経歴を持つ。
日本の物流業界では、2024年4月から「働き方改革関連法」によりトラックドライバーの時間外労働規制が強化され、人手不足や輸送力不足が深刻化している。国土交通省や業界団体も今後の輸送力不足を懸念しており、特に長距離大量輸送を担う幹線領域での自動運転技術の社会実装が急務とされる。加えて、EC市場の拡大や消費地の多様化により、幹線輸送とラストワンマイルの連携強化も求められている。
自動運転トラック分野にはDaimler Trucks、日野自動車、いすゞ自動車といった大手メーカーが参入し、連携体による開発が進んでいる。DeNAなどモビリティ分野の企業も関連領域に関与しており、ロボトラックはスタートアップ特有の迅速な開発サイクルで実証を重ねている。経済産業省などの調査では、国内のロボット関連市場は2030年代に10兆円規模へ拡大するとの予測もある。物流現場はAIロボティクス応用の重要分野として位置付けられている。
今回の資金調達にはシードラウンドおよびプレシリーズAラウンドが含まれ、初期投資家として東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC)、PKSHAアルゴリズム2号ファンド、AIS CAPITALが名を連ねる。その後、グロービス・キャピタル・パートナーズやオリックスなども出資に加わった。新たにJICベンチャー・グロース・インベストメンツおよびSMBCベンチャーキャピタルが資本参加したことで、スタートアップの成長と社会インフラとしての普及促進への期待が高まっている。調達資金はプロダクト開発や事業開発体制の強化に活用される予定だ。
2025年7月に発表されたオリックス自動車との業務提携では、全国規模の車両ネットワークや顧客基盤を生かし、自動運転技術を用いた物流事業者向けサービスの共同開発と早期提供を目指している。また、経済産業省の実証支援事業を活用し、段階的に走行実証と社会受容性の向上を図る計画である。
自動運転トラック分野では、都市間長距離の幹線輸送や夜間・深夜運行、省人化など定型業務から順次実用化が広がる見通しだ。AIによる燃費最適化やルート選定、自動車の電動化との連携も今後の重要テーマとなる一方、安全基準認証プロセスの確立、交通インフラとの連携、既存物流現場への適応といった課題も残されている。国際的な競争環境下で、技術標準化や国内外プレイヤーとの連携強化も論点となっている。
ロボトラックは、完全無人運転トラックの量産化および社会実装を目指して新たな実証エリアでのサービス提供準備を進めている。自動運転トラックの社会実装が物流業界の構造転換と新たなインフラの形成につながる可能性を示しつつ、産業界全体の関心が高まっている。