株式会社リトプラ

次世代型テーマパーク「リトルプラネット」を国内外に展開する株式会社リトプラは、2025年6月から8月にかけてシリーズCラウンドの資金調達(額は非公開)を実施した。
GENDA GiGO Entertainment、タカラトミー、小学館、トーハン、広島ベンチャーキャピタル、Life Design Fund、そしてソニーイノベーションファンドの計7社から出資を受けた今回のラウンドは、事業会社との連携を重視した戦略的な調達となった。
「アソビでミライをつくる」をミッションに掲げる同社は、2016年9月の設立以来、テクノロジーと遊びを融合した体験型施設を運営している。現在国内24か所、海外4か所に常設パークを展開し、累計来場者数は350万人を突破した。
これまでの資金調達では、2018年2月にTBSホールディングスをリード投資家として総額約6億円を調達し、2019年11月にはKDDI Open Innovation FundやOLMベンチャーズが参画した約6億円のシリーズBラウンドを実施。その後も複数の資本業務提携を通じて事業基盤を強化してきた。コロナ禍で3年間苦戦したが、2023年から業績が回復軌道に乗り、今回のシリーズCラウンドで事業加速を図る。
代表取締役CEOの後藤貴史氏は、ポケラボ創業後にグリーへのバイアウトを経験した連続起業家だ。今回の資金調達の狙いと今後の事業戦略について聞いた。
年間130万人利用の4ブランド運営モデル
――御社の事業概要について教えてください。
後藤氏:事業は大きくB2CとB2Bの2つを展開していますが、特に直近はロケーションベースエンターテインメント(LBE)事業に注力しております。現在4つのブランドを運営しており、主力は12歳以下の子どもとそのファミリー向けの「リトルプラネット」ですね。
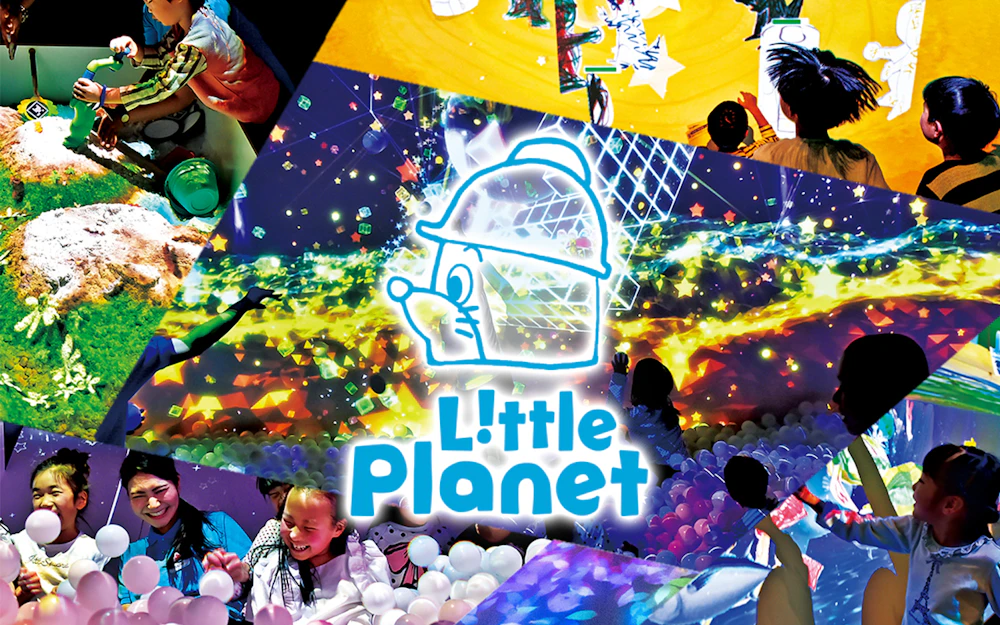
それ以外には、読み聞かせをテーマにした「Muchu Planet」、タカラトミーとの資本業務提携のきっかけとなった「タカラトミープラネット」があります。タカラトミープラネットは、トミカやプラレール、ベイブレードといったおもちゃを体験できる施設で、おもちゃを持ち込んで遊んだり、初めておもちゃに触れる場所として機能する体験型のおもちゃ屋さんなんです。
重視しているKPIは大きく2つで、坪売上と顧客満足度(NPS)になります。施設の平均滞在時間は65分となっており、施設規模は100坪〜200坪程度が平均的ですね。ターゲットは2歳〜12歳ですが、ボリュームゾーンは7〜9歳の子どもたちとなっています。現在の会員数は40万世帯で、アプリ「プラネットポータル」を通じてデータ管理を行っているところです。
――法人向けのB2B事業についても教えてください。
法人向けには、当社が開発したコンテンツやソリューションを提供中です。商業施設やホテル、自治体からの依頼でイベントコンテンツを制作することが多く、例えば毎年開催されるトミカ博の一部コンテンツや、三井不動産のグランピング施設内のアクティビティなども手がけているんです。
また、トヨタ自動車レクサスや三井不動産といった大手企業とも取引しており、裏方として支えることが多いため表に出ることは少ないのですが、着実に実績を積み上げているところです。
ゲームエンジン活用でコンテンツ60種を全拠点同時アップデート
――技術面での競合優位性について聞かせてください。
最大の特徴は、企画から開発、運営まですべてを内製で行っていることですね。フルタイムで50名の社員のうち半数がクリエイターで、そのクリエイターの8割がゲーム業界出身というメンバー構成となっております。
現在60種類ほどのコンテンツを保有していますが、これらを全国・海外問わず一斉にアップデートできる仕組みを構築しました。一般的なプレイグラウンド型施設では、各店舗で異なるコンテンツを配置することが多いのですが、当社はソフトウェア開発に強みがあるため、マトリックスのように全店舗を同時アップデートできるんです。
例えば夏休み期間限定のイベントを1〜2か月の期間限定で展開する場合、全拠点で同時にコンテンツを変更し、期間終了後は元に戻すことが可能になります。年間で3〜4回のメジャーアップデートを実施しており、ディズニーランドに近いアプローチで季節連動のコンテンツ更新を行っています。
裏側の基盤技術はゲームエンジンをベースに構築しているため、ゲーム開発者であれば比較的容易にソフトウェア開発に参加できる環境を整えています。特にこだわっているのは、体を動かしたり砂を掘ったりといった物理的なアクションを、リアルタイムでセンシングして映像に反映させる技術です。

センシングされたデータをどれだけラグなく、美しく表現できるかは、長年のノウハウの蓄積が必要な領域です。例えば壁に触れてから反応が返ってくるまでの時間や、複数人が同時に触れた際の認識精度など、体験する方にはすぐに分かる違いが生まれます。
また、「シャリング」というリストバンドシステムを導入しており、子どもが腕に装着したリストバンドに内蔵されたNFCチップとスマートフォンをペアリングして使用するんです。遊んだデータが半自動的にスマートフォンに記録され続けるため、東京の店舗で遊んだ子どもが夏休みに実家に帰省した際に遠方の当施設を利用しても、データを紐づけて継続的な体験を提供できるという仕組みになっています。
――コンテンツ開発のプロセスについて聞かせてください。
これまではプロダクト主導で、クリエイターやエンジニアが主体となってコンテンツを開発してきました。年に2回「ハッカソン」という社内イベントを開催し、エンジニアが最新技術を使ったプロトタイプを開発し、それを実際のコンテンツに発展させるR&Dの取り組みを続けています。
ただし、必ず子どもレビューは実施しています。新コンテンツを店舗に設置する前に、社員の子どもや外部から呼んだ子どもたちに実際に体験してもらうんです。子どもの反応は非常に分かりやすく、面白くないコンテンツには反応しないため、その場合は作り直すこともあります。
最近は顧客が増加し、クリエイティブの経験がないメンバーも入社する中で、もっと顧客に向き合うべきではないかという議論も出ているところです。プロダクト主導を維持するか、顧客視点をより重視するかは、現在社内でも議論を進めている状況ですね。
ポケラボ売却後の連続起業、XRと子供向け事業の融合から誕生
――御社の創業背景について教えてください。
私は2007年に学生ベンチャーとしてポケラボという会社を立ち上げ、2012年にグリーにバイアウトしました。その後2016年まで在籍していましたが、社長は既にバトンタッチしていたので、一般社員として退職し、新たにリトプラを設立したんです。
当初からやりたかったのはディズニーランドのような新しいテーマパークモデルの創造でした。創業時、私がXR事業をやりたいと考えていた一方で、創業メンバーの鈴木が子ども向け事業に取り組みたいと考えていたんですね。この2つのやりたいことを融合させて生まれたのがリトルプラネットになります。

公園のような場所をデジタル化して新しく作りたいというところからスタートしました。公園の持つコミュニティとしての良さや、近所の子どもたちが集まって仲良くなれる環境は残しつつ、より安全でより面白い体験を提供したいと考えたのです。
――市場環境の変化についてはいかがでしたか。
コロナ禍では「なぜリアル施設をやるのか」とよく言われましたね。メタバースが注目される中で、デジタル版リトルプラネットを作らないのか、という提案も多数いただきました。
しかし、結果的にはリアルな業態を信じてやってきて良かったと思っています。実際、コロナ前よりもマーケット自体が大きくなっていると実感しており、来場者数も明らかに増加しているんです。私たちの体験の中心にあるのはフィジカルな要素、つまり触ったり、何かを作ったりという体験の良さで、これはデジタルだけでは代替できない価値だと改めて確信しているところです。
事業会社7社と資本業務提携、現場レベル連携を重視
――今回のシリーズCラウンドの特徴について教えてください。
今回の調達は資金調達というよりも、各社との事業シナジーや業務提携に主眼を置いています。例えばタカラトミーとGENDA GiGO Entertainmentの2社とは資本業務提携を締結し、より密接な連携体制を構築しました。
タカラトミーとは「タカラトミープラネット」という新業態を共同展開しており、トミカやプラレール、ベイブレードといった同社のおもちゃを体験できる施設を運営中です。
GENDA GiGO Entertainmentは海外展開のパートナーで、台湾やベトナムでの出店を手がけています。今回の資本業務提携により、海外展開をさらに加速させていく予定です。
また、ソニーや小学館といったIPを持つ企業とは、それぞれが保有するIPとの連携や、当社が今後IPを自社で保有していくためのキャラクターやストーリーテリングの共同開発を進めているところです。各社ごとに個別の協業プランを作成し、毎月お互いの進捗をぶつけ合ってシナジーを創出しているという状況ですね。
――事業会社との連携において重視していることはありますか。
現場レベルでの関係構築が非常に重要だと考えております。CVC部門や財務部門とのコミュニケーションだけでは、実際のシナジー創出は難しいからなんです。タカラトミーでは全ブランドの責任者の方とコミュニケーションを取っていますし、GENDA GiGO Entertainmentでも現場の方と密に連携しています。
お互いのやりたいことと制約をしっかりすり合わせた上で、財務の方も含めて事業を推進していくスタンスですね。資金を入れていただくだけでなく、そこから価値を上げていくために、定期的なコミュニケーションと現場同士のコミットメントが重要になります。
また今後は、ロケーションを既にアセットとして持つ企業と積極的に連携していきたいですね。これらの企業は競合ではなく、むしろ一緒にフランチャイズを生み出していくパートナーとして捉えており、お金を出してご一緒していくことも含め、ぜひお話ししていきたいと考えております。
2028年60拠点展開目標、アジア・中東・米国への海外進出加速
――海外展開の状況はいかがですか。
現在、台湾、ベトナム、インドネシアで展開しており、来月には中国での展開も控えているところです。海外比率を15〜20%まで高めたいと考えており、サウジアラビア、UAE、アメリカなどからも引き合いをいただいております。今後3年以内には10拠点を新たに開設する計画ですね。
ただし海外展開は直営ではなく、現地パートナーとの協業が中心となります。台湾が成功モデルとなっており、日本のコンテンツをほぼそのまま展開しても現地で受け入れられることが実証されました。宗教的な配慮以外では、大きな変更を加えずに展開できているんです。
――今後の中長期的な展望について聞かせてください。
私たちの最終的な目標は「ディズニーランドのような新しいテーマパークモデル」の創造です。リトルプラネットは、ディズニーランドでいうトゥーンタウンのような、ファミリーに特化したエリアを切り出したものと捉えております。

今後は、もう少し大人も楽しめるアドベンチャーランドのような施設や、テーマごとに特色のある拠点を全国に分散配置していく「分散型テーマパーク」構想を進めているところです。アプリ「プラネットポータル」を通じて世界観は共通化されているため、どの拠点でも同じサービス品質を提供しつつ、各施設は固有のユニークなテーマを持つというモデルになります。
私が目指しているのは長期的に続く会社です。現在の子どもたちが10年、20年後にカップルとして施設を訪れたり、自分の子どもを連れてきたりするような──2世代、3世代に渡って愛されるブランドを作りたいと思っています。そのためにも、IPは自社で保有していきたいと考えており、YouTubeでキッズアニメを展開する会社への出資も行いました。
アメリカではロケーションベースエンターテインメント領域でNEONやLighthouse Immersiveといった企業が注目されており、これらの日本版を目指したいと考えています。技術に強みを持つ企業として、新たな体験価値を創造し続けていきます。










