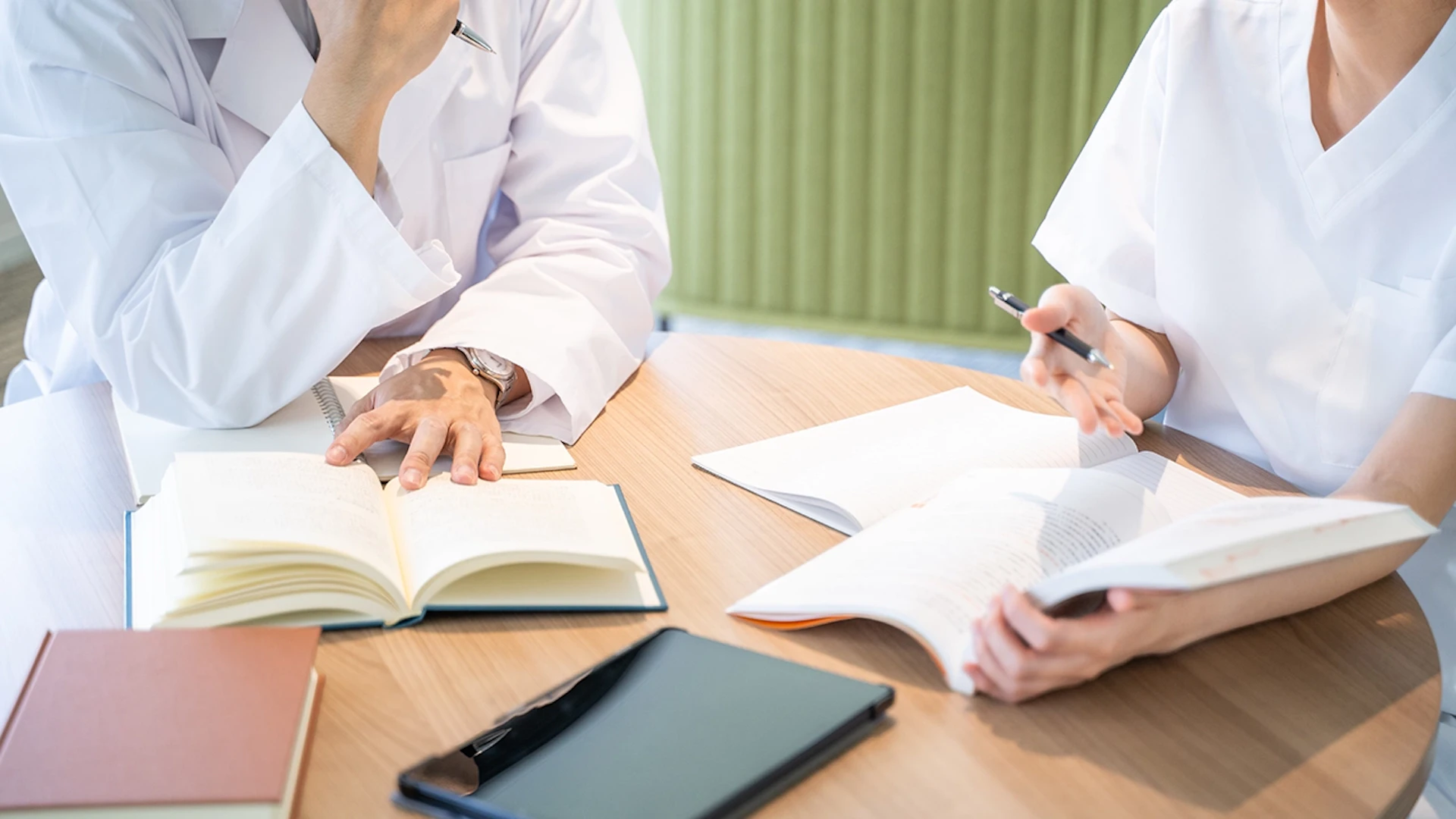amu株式会社
%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9CEO%20%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%BA%83%E5%A4%A7.jpg?fm=webp&fit=crop&w=1920)
宮城県気仙沼市に拠点を置くスタートアップ、amu株式会社は、廃漁網を原料とするリサイクル生地「amuca® Fabric」を2025年11月5日より発売することを発表した。
同製品は、漁網の回収からケミカルリサイクル、素材化・製品化までの全工程をトレーサビリティとして可視化する仕組みを備えており、QRコード付きの「amuca®タグ」を通じて、素材の出所(どの漁具、どの地域、どの提供者)を消費者が確認できる。今回の発表は、リサイクル素材を巡るサプライチェーンの透明性確保という観点でも注目される。
amuは、2023年5月に設立された、宮城県気仙沼市発のスタートアップである。主に廃漁網を回収・再資源化し、新たな素材・製品へとアップサイクルする事業を展開する。回収された漁網は、分別・ケミカルリサイクル等の工程を経て、再びナイロンなどの繊維に生まれ変わり、「amuca®」という素材ブランドとして販売されている。
代表取締役 CEOの加藤広大氏は、大学在学中にサイバーエージェントでインターンを経験。その後、大学3年時に中退して同社へ入社し、AbemaTVの番組プロデューサーを務めた。大学時代、教授の勧めで夏休みに初めて気仙沼市を訪れたことをきっかけに地域の魅力を感じ、これが後の転機となる。2019年に気仙沼へ移住し、廃漁具のアップサイクル事業を検証。そして2023年5月に、こうした経験をもとに「amu」を設立した。
世界的に、衣料品・繊維産業は大量生産・大量消費構造の中で環境負荷が高い産業と指摘されており、廃棄プラスチックや海洋ゴミ等の課題が顕在化している。実際、日本の海岸に漂着している海洋プラスチックごみのうち、漁業関連ごみが質量ベースで59.5%を占めるといわれている。
こうした状況を受け、繊維業界ではリサイクル素材の活用や生産プロセスの見直し、そしてトレーサビリティ開示が急務となっている。特に欧州ではデジタルプロダクトパスポート(DPP)制度の導入等、素材・製造工程の透明性を義務づける方向も出てきており、本件のような「素材の源流までたどれる」取り組みは、業界内でも注目されている。
今回発売となる「amuca® Fabric」は、廃漁網の回収から製品化までを一社で一気通貫で管理・可視化する仕組みを有する点が特徴である。第一弾として70デニールのナイロンタッサー素材(撥水加工)を用い、トートバッグ・サコッシュ・キャップなどのアパレルグッズ、さらにはアウトドア用品にも適用可能な高機能素材として提供される。
また、回収・製造の過程において、どの地域の漁具がどのように生まれ変わったのかを、漁師や地域との連携まで含めて開示する点を特徴としており、単なる素材再利用の枠を超えた「物語性」や「透明性」を重視している。
今後、amuが掲げる「いらないものはない世界をつくる。」というビジョンを背景に、「amuca® Fabric」の導入がどの程度、アパレル・アウトドア・マテリアル業界に波及するかが注目される。消費者・ブランド双方が素材の源流まで確認できるという仕組みは、トレーサビリティ対応が重要視される中でのひとつの指標となり得る。
加えて、回収→製造→販売の一気通貫のサプライチェーン構築というモデルが、地域発スタートアップとしてどれだけスケールできるか、今後の展開も併せて注視すべきである。
画像はamuプレスリリースから