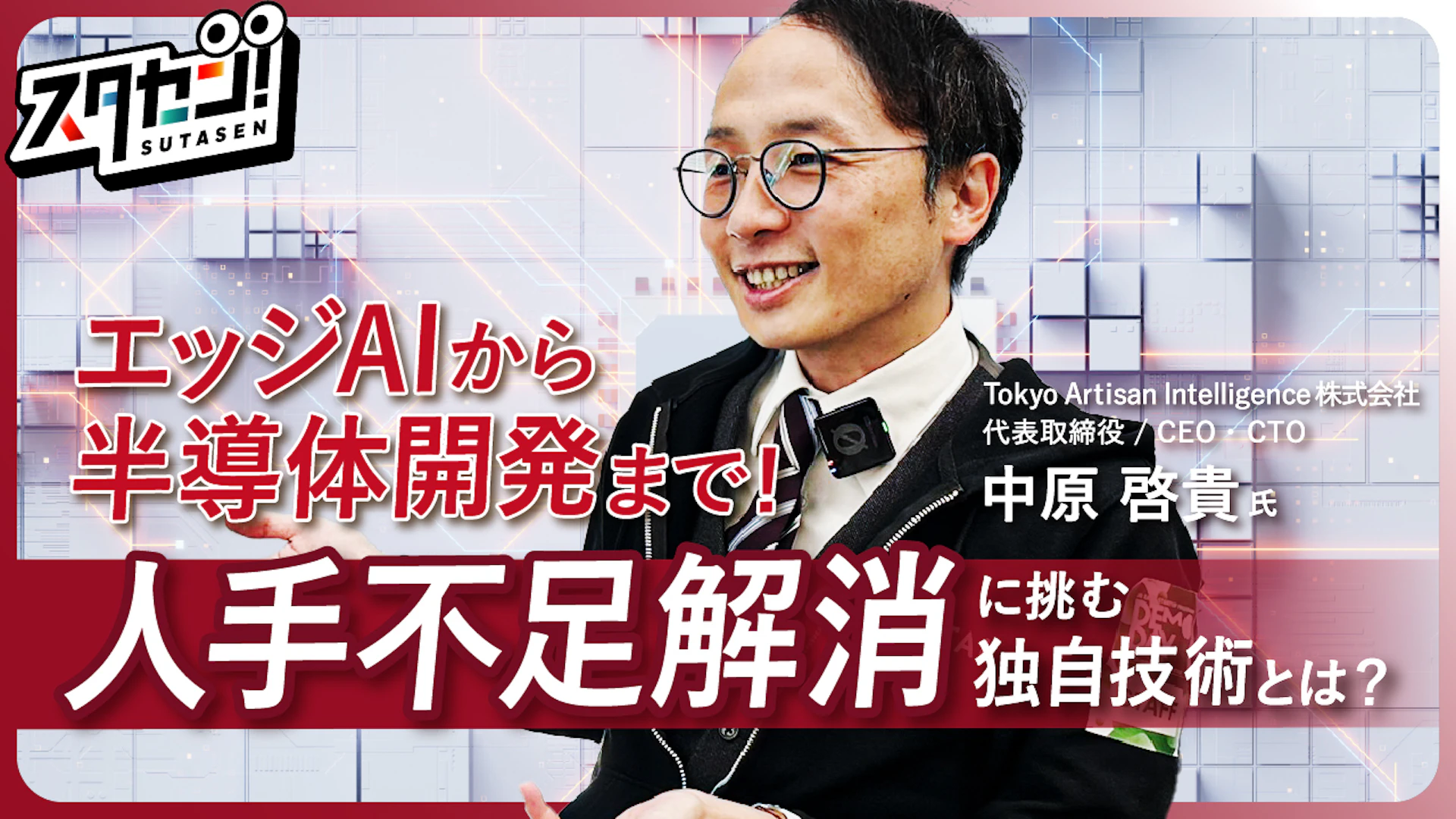株式会社EVERSTEEL

こんにちは!ケップルが運営するYouTubeチャンネル「スタセン!(スタートアップ潜入チャンネル)」制作チームです。今回は、鉄鋼業界の課題解決に取り組む東大発ディープテックスタートアップの株式会社EVERSTEELを取材しました!
鉄鋼の脱炭素をAIで実装する──EVERSTEELの挑戦
東京大学発のスタートアップEVERSTEELは、鉄鋼リサイクルにAIを導入し、環境課題の解決に取り組んでいます。鉄鋼業は産業界で最大のCO2排出源とされており、同社は電気炉(電炉)による鉄スクラップ循環を促進することで、脱炭素化の加速を目指しています。
主力のAIシステム「鉄ナビ検収AI」は、鉄スクラップの品質判定や異物検出を自動で行えるのが特徴です。これにより、高炉法から電炉法への移行を後押しし、CO2排出量の大幅な削減を実現することを目指しています。

今回の動画では、東京大学アントレプレナーラボにある同社オフィスに伺い、代表取締役の田島 圭二郎氏、共同創業者/COO 佐伯 真氏にインタビューしました。同社の開発する「鉄ナビAnalytics」や今後の展望などについて詳しくお話いただきました。本記事ではその内容をご紹介します!
鉄スクラップに潜む“不純物混入”をAIで解決する挑戦
――事業概要について教えてください。
田島氏:私たちは鉄鋼業界向けに画像認識AIのサービスを展開している会社です。特に、鉄をリサイクルする「電気炉メーカー」と呼ばれる企業向けにプロダクトを提供しています。
電気炉メーカーでは、原料となる鉄スクラップにさまざまな不純物が混入してしまうことが避けられません。そこで私たちは、画像認識AIを用いて不純物を自動で検知し、除去することで、リサイクルを促進していくプロダクトを開発しています。

――事業をはじめられた背景は?
実は、全ての産業の中で最もCO2を排出しているのが鉄鋼業です。そのため、何とか排出量を減らしていく必要があります。鉄はリサイクルによって製造することで、CO2排出量をおよそ4分の1に抑えることができるため、非常にクリーンな作り方といえます。
しかし現状として、リサイクルがなかなか進まない理由があります。それが「不純物の混入」です。リサイクルは、もともと廃棄物であるスクラップを原料に再び鉄へと生まれ変わらせる工程なので、どうしてもさまざまな異物が混じってしまいます。これをしっかりと除去して、きれいなスクラップにしなければリサイクルの促進は難しい。だからこそ、この分野には技術革新が必要だという考えからです。
スクラップに含まれる不純物を取り除かないと、品質基準に引っかかってしまいます。たとえば銅は鉄と相性の悪い元素としてよく知られていますが、わずか0.4%以上混入するだけで、出来上がった鉄の表面が割れてしまうのです。結果として、その鉄はすべて不良品となり、廃棄せざるを得なくなってしまいます。
なぜ鉄鋼業なのか?──脱炭素の最大課題に挑む理由
――鉄リサイクルに興味を持たれたきっかけは?
もともと私は大分の出身で、実家は鎌倉時代から続く林業を営む家系です。林業は環境にとても良いのですが、森林が吸収できるCO2に対して、人間が排出しているCO2は非常に多いんです。森を守るだけでは脱炭素は実現できないと感じ、どこが一番排出しているのかを見ていく中で、解決したい対象として鉄鋼業に行き着きました。そこで、鉄のリサイクルを促進することで脱炭素を実現したいと考えるようになりました。
――一見するとかけ離れているように感じる「鉄リサイクル」と「AI」ですが、この取り組みに至った経緯は?
私が学生だった頃、AI技術が台頭し、画像認識などが情報系の学生や専門家でなくても触れられる段階まで来ていました。私はもともと鉄リサイクルを研究する材料系の立場でしたが、「AIを掛け合わせれば新しい分野を切り開けるのでは」と考えるようになりました。そこで、興味本位でAIを組み合わせ始めたことが、この取り組みのきっかけです。
また、大学からのサポートにも非常に助けられました。東京大学のプログラムに採択いただいたことで、まだ会社として立ち上がる前の段階からさまざまな支援を受けることができました。その活動が日本国内の鉄鋼メーカーの目にとまり、いくつかお客様になりそうな企業とのつながりも生まれました。そうした後押しがあって、なんとか会社として立ち上げることができた、というのが背景です。
――解決を目指す現場の課題。
実は現場には、驚くような課題が潜んでいます。鉄スクラップをリサイクルする工場では、毎日原料として購入するスクラップを熟練の作業員が「目検」でチェックしています。ところが、1人の熟練者が1日に扱う量はおよそ300トン。圧倒的な物量に加え、スクラップはぐちゃぐちゃに混ざった状態のため、その中から不純物を見つけ出す作業は非常に難易度が高いのです。
ひたすら大量のゴミがあるような状況の中から、その中でも危険な不純物だけを見つけ出す。現場の作業はまさにそのようなイメージです。見分け方には明確な基準がなく、ほとんど見極めようがないものを、10年20年と積み重ねた熟練者のノウハウで何とか対応してきたのが実情でした。さらに、一人前になるまでには最低7年ほどの育成期間が必要で、その間に退職されるケースもありますので、採用コストや育成コストも大きな負担となります。非常に深い課題です。
こうした現場の課題を、もっと簡単に、そして高精度に解決していこうというのが、私たちの取り組みです。
――新サービス「鉄ナビAnalytics」について。
今回リリースした「鉄ナビAnalytics」は、現場に眠っていたデータを可視化し、それを分析することで、より良い操業につなげる機能です。現状では、鉄スクラップの目検チェックを支援するシステムの追加機能として展開しており、特にスクラップ購買に関するデータの可視化を進めています。
例えば、毎日どのくらいの数量のスクラップを、どのグレードで、誰が購入したのかといった情報を分析できるようになります。一見すると当たり前に思えるかもしれませんが、鉄鋼メーカーをはじめ製造業の現場では、こうしたデータが部署ごとに紙で蓄積され、ほとんど可視化されていません。クラウド管理はもちろんされていないのが実情です。
また、ヒューマンエラーのリスクもあり、こうしたデータを管理する現場の方々の仕事はますます大変になっています。だからこそ、ITと非常に相性が良い領域だと考えています。
それらの情報を一つ一つクラウド化し、可視化して分析につなげることが、最終的には大きなインパクトをもたらすと考えています。

――提供プロダクトの強みや特長。
佐伯氏:弊社の強みは、画像解析や撮影といった技術そのものだけでなく、現場のベテランの方々が長年培ってきた専門知識をいかに抽出し、技術に落とし込むかという点にあります。
これまで書面化されていなかった知見もヒアリングを重ね、自分たちでカタログも一から作り上げていきます。そこには何十種類、何百種類にも及ぶ素材や部品の情報が含まれています。例えば「モーターには銅が多く含まれており、鉄に混ざるとこういう影響が出る」といった内容まで資料化し、それをAIに覚え込ませています。
さらに、こうした知識を正しく技術に反映させるために、セールスメンバーだけでなく開発メンバーやAIの学習用データセットを作成するメンバーも現場に足を運びます。専門現場で直接知識を得る取り組みを繰り返すことで、現場に根ざした技術開発を進めています。
こうした専門知識を技術として体系化し、AIに落とし込むための数えきれない工夫こそが、弊社のプロダクトの特長であり、強みだと考えています。
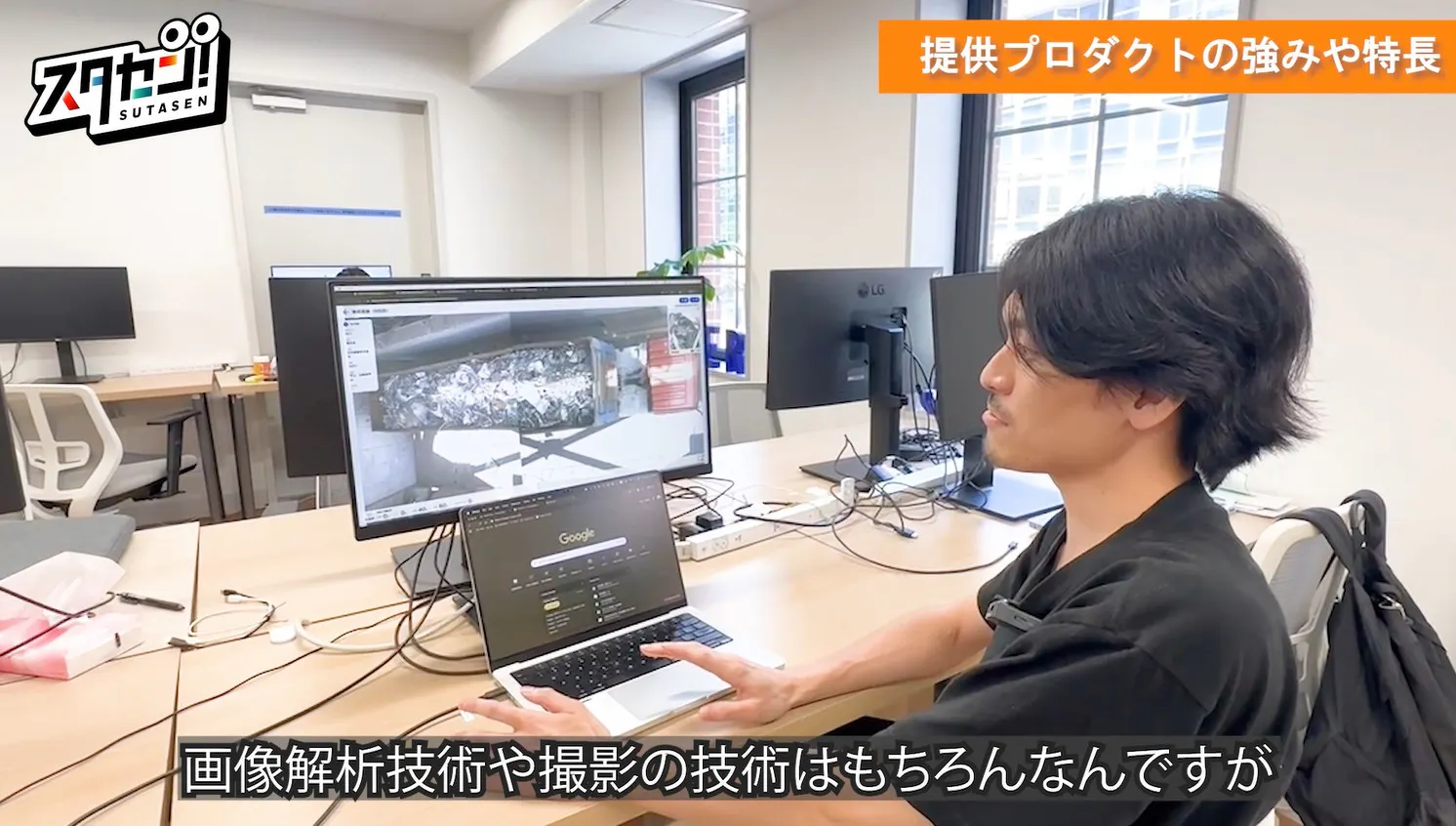
日本発のAI技術で、世界の鉄鋼リサイクルを変える
――今後の展望は。
田島氏:私たちのプロダクトは昨年完成を迎え、今年に入って拡販期に入りました。現在は、形になったプロダクトを新しいお客様へ広げていくフェーズで、収集できるデータ量も増え続けており、それに伴って精度も日々向上しています。
今では、日本で流通するスクラップのおよそ20%を毎日カメラで撮影できるようになっています。まずは国内でのシェアをさらに拡大していくことが第一の目標です。
その先には、東南アジアやインド、中国といった市場を見据えています。鉄スクラップのチェックに関する課題は、国が違ってもほとんど共通しています。ですので、海外にも展開し、世界的な規模でリサイクルを促進し、脱炭素につなげていく。それが今後の展望です。
動画では採用情報についてもメッセージをご紹介!
同社は、現在積極的に採用活動を行っているということで、代表の田島氏より最後に採用に関するメッセージも伺っています。ぜひ動画でご視聴ください!
「スタセン!」では今後も注目スタートアップを取材していきます。次回もぜひお楽しみに!
掲載企業
Writer

「スタセン!」制作チーム
「スタセン!」制作チーム
ケップルが運営するYouTubeチャンネル「スタセン!(スタートアップ潜入チャンネル)」制作チーム。注目スタートアップ企業に潜入取材し、その開発技術やサービス、企業の魅力を紹介する。
Tag