株式会社TeaRoom

日本茶を現代の日常に浸透させる挑戦
近年、国内外で日本茶の価値が見直されている。農林水産省のデータによると、2024年に緑茶の輸出額は364億円と過去最高額を記録しており※1、海外市場でもその需要が高まっている。一方で、国内の茶産業は高齢化や茶価の低迷により厳しい状況が続いており、産地の持続可能性や消費スタイルの転換が課題とされている。
そうした中、伝統文化としての「日本茶」を再解釈し、現代のライフスタイルやグローバルな健康志向に適合させようとするスタートアップが増えている。製造工程の透明化やサブスクリプション、体験型サービス、グローバル展開といった新たなアプローチを通じて、従来のお茶の枠組みを超えた提案が広がりつつある。
本記事では、日本茶の持続可能性や新たな価値創出に取り組むスタートアップ5社を紹介する。
.jpg?auto=compress&fm=webp&w=2667&h=612)
スタートアップ5選
株式会社TeaRoom
株式会社TeaRoomは、日本茶の製法を基にした嗜好品の開発・販売や、茶の湯文化を生かした事業プロデュースを手がける会社。2020年には農地所有適格法人・株式会社THE CRAFT FARMを設立し、茶葉の生産から商品化、販売までを一貫して行うことで、持続可能な茶業の実現を目指している。
代表取締役CEOの岩本涼氏は裏千家の茶道家でもあり、伝統を尊重しつつ現代のライフスタイルに合った日本茶の新たな楽しみ方を提案。オフィス向けの「オフィスで茶の間」など、日本茶を日常に取り入れるサービスの提供にも取り組んでいる。
World Matcha株式会社
企業HP:https://cuzenmatcha.com/ja-jp
2019年2月設立。アメリカ・カリフォルニア州にも拠点を持ち、グローバルな視点で事業拡大を行っている。主な事業として、抹茶マシンとオーガニック抹茶リーフを提供する「CUZEN MATCHA(空禅抹茶)」を展開。誰でも挽きたての抹茶を手軽に楽しむ機会の創出とともに、日本の茶農家の持続性を担保するビジネスを行っている。
2024年1月に7億円以上の資金調達を実施。近年の健康志向の高まりやアメリカでのブームを背景に、今後も成長が見込まれる。
D-matcha株式会社
企業HP:https://dmatcha.jp/
京都・和束町を拠点に日本茶の生産から加工、販売、体験プログラムの提供までを一貫して行うスタートアップ。自社茶園で育てた茶葉を使用し、無添加・無香料にこだわった抹茶・煎茶などの製品を展開するほか、カフェの運営を通じて「茶のある暮らし」を体験として提供している。
農業・観光・食を横断する6次産業化を進めることで、地域資源を活かした持続可能なビジネスモデルを構築。代表の田中大貴氏は京都大学農学部を卒業後、米国Babson CollegeでMBAを取得しており、国内外に向けて日本茶の魅力を発信している。
株式会社ユノミライフ
企業HP:https://yunomi.life/ja/pages/yunomilife
日本茶の生産者と世界中の消費者をつなぐオンラインプラットフォーム「Yunomi.life」を運営する企業。Yunomi.lifeは、日本全国150以上の小規模な茶園や生産者と提携し、煎茶、玉露、抹茶、和紅茶、番茶など多様な茶種を含む1,000種類以上の商品を取り扱う。ユーザーの9割が海外在住者で、世界90カ国以上の個人や卸売業者に向けて販売されている。「人から人へ」の商取引をポリシーとし、生産者のお茶づくりにかける情熱や工夫を伝えることを重視している。
2025年、社名を株式会社MATCHA LATTE MEDIAから株式会社 ユノミライフに変更した。
nokNok株式会社
企業HP:https://noknok.life/
「時間をかけて味わう」をコンセプトに、消費体験を生み出すECプラットフォーム『nokNok』の開発・運営を行う企業。2024年からは、茶畑のオーナー制度を通じて茶のある暮らしを提案するプロジェクト「OCHA Owner」を始動。消費者が茶畑の一部を所有し、定期的にイベントに参加することができたり、オーナーである茶畑の茶が届いたりするサービス。茶の製造にかかるコスト増加により存続が危ぶまれる茶農家の支援も目的としている。
茶そのものの価値だけでなく、育成・収穫・製茶といった過程を物語として届けることに重きを置いており、現代のライフスタイルに合ったプロセス消費型の日本茶体験を提案している。
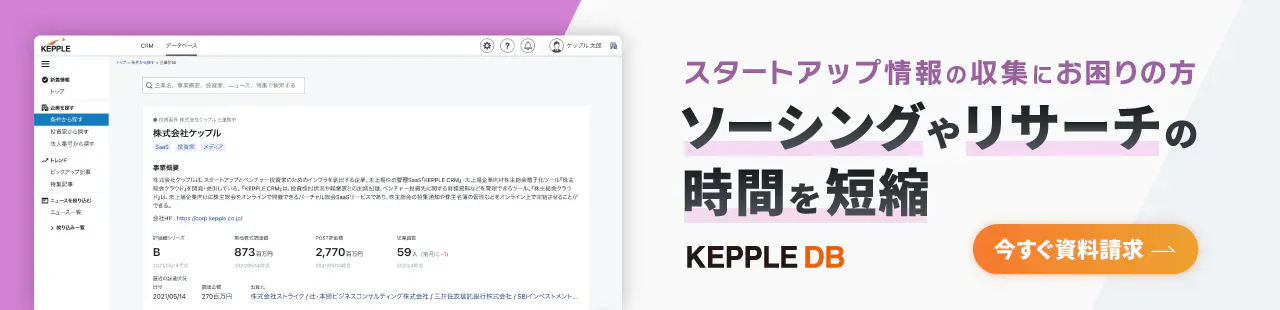
-----------
※1 農林水産省:「お茶の輸出入の動向」










