オリエンタルランド・イノベーションズが語る新規事業創出を目的としたCVC戦略──出資から出向、新規事業創出に向けた取り組み
.webp?fm=webp&fit=crop&w=1920)

※本記事は、株式会社ケップルが2025年8月26日に実施した「成熟産業でのスタートアップ共創戦略 社内連携のリアル」に関するセミナーレポートになります。
近年、事業会社において、オープンイノベーションや新規事業開発の取り組みが増加している中で、「社内をどう巻き込むか」が大きな課題として浮上しています。特に、協業や新しい取り組みを推進する立場の人にとっては、理解を得るべき関係者が多く、調整や連携の難しさに直面するケースが少なくありません。
今回は、戸田建設株式会社の斎藤寛彰氏をお招きし、ケップルの江口がモデレーターを務めて開催したセミナーのレポートをお届けします。
創業140年超の歴史ある戸田建設は、15社8ファンドへの出資と617件の事業部紹介という豊富な実績を持っています。この成果を支える社内連携の実践的なノウハウについて、理解を深めていただける内容となっていますので、ぜひご覧ください。
▼スピーカー紹介
斎藤寛彰 氏 戸田建設株式会社|ビジネスイノベーション部 共創投資課|課長
東京工業大学大学院修了後、戸田建設に入社。建築施工管理、エンジニアリング等を経験後、戦略企画等を経て、現在は国内外の優れたスタートアップ企業への投資とオープン・イノベーションに取り組む。建設DXや建設×イノベーション領域での研究活動にも取り組む。2017年頃からオープン・イノベーション活動を開始し、2020年からCVC投資活動を本格化。現在までに3143社の情報収集、617件の事業部門への紹介を行う。
ー 戸田建設グループがオープンイノベーション活動に取り組まれている背景について教えてください。
斎藤氏:弊社は建築、土木、不動産、再生可能エネルギーなど幅広い事業を展開していて、オフィスビル、生産施設、医療施設など様々な建物を手がけています。
ここで問題となるのは、それぞれの建物の発注者が全く異なるニーズを持っていることです。例えばオフィスでは働きやすさの視点の要求が多くあったり、生産施設には効率性やセキュリティが、医療施設には安全性や快適性が重要になります。建物を建てるだけでなく、その中でのオペレーション改善や環境づくりまで含めて考えると、自社だけですべての領域の専門知識や対応する技術を持つのは現実的ではありません。
そこで、各分野に特化したスタートアップ企業と連携することで、お客様により価値の高いソリューションを提供できるのではないかと考えました。これがオープンイノベーション活動を始めた発端です。
ー 2020年からCVC投資を開始されていますが、それ以前の社内での理解度はいかがでしたか?
実は2020年のCVC開始前に、3年間の準備期間がありました。2017年頃から前身の部門で、主に海外のスタートアップのテクノロジーを探索して、自社がユーザーとなった検証(いわゆるベンチャークライアントモデルのような取り組み)を積み重ねてきたんです。
ただし、当時社内では、オープンイノベーションというアプローチはそれほど理解されていませんでした。言ってみれば「有志による活動」という感じでした。
そこで、この活動をどう会社の経営戦略に組み込んでいくかを考えながら、3年間かけて着実に実績を積み上げていきました。2020年にCVC投資活動について会社に承認頂けたのは、これまでの取り組み実績があったことによる信頼もポイントになったのではないかと思います。
ー CVCの投資枠設定についてはどのように進められたのでしょうか?
投資枠を決めるにあたって、他社CVCの投資金額や期間について可能な限り情報収集しました。投資額の設定には明確な答えはないのですが、合理的に金額を設定する上でなにか論拠となるベンチマークが必要でした。
金額が少なすぎるとスタートアップへのインパクトが不十分ですし、多すぎると「運用が目的化している」「立ち上げ段階のチームには過大すぎる」と批判的に見られてしまうリスクもあります。他社の投資枠や投資ペースを参考にして、3年で30億円、年間10億円程度の投資ペースを投資額の上限とする提案をしました。
30億円という金額は私たちのチームとしてはとても大きな金額ですし、投資したスタートアップの経営が上手くいかないリスクもそれなりにあります。そのため、上司や経営層には丁寧に説明していきました。30億円の投資枠を設定する意味として、リスクを一定範囲に抑える目的があることを強調しました。加えて「イノベーションの取り組みを積極的に行わない」リスクについてもコミュニケーションをとっていきました。
これにより、CVCの投資活動は、リスクを一定範囲内に抑えつつオープンイノベーションを加速する取り組みとして承認して頂くことができました。
ー オープンイノベーション活動を社内で推進・浸透させていくうえで、事業部とのコミュニケーションはどのように進められましたか?
一言で言うと、事業部から「嫌われないように」活動することを徹底しています。
事業部の立場から考えてみると、日々の業務やプロジェクトが進んでいる中で、横から「こんな新しいテクノロジーがあります」「これを導入してみませんか」と提案されるのは、人によってはストレスになります。特に忙しい時期やプロジェクトの途中でそういう提案をすると、完全にノイズになってしまいます。
だからこそ、私たちは立ち位置を明確にしています。オープンイノベーションチームには最終的に製品やサービスを導入する決定権はありません。決定権は事業部が持っていて、我々はあくまで「サポートする立場」です。
もし自分たちが主役になろうとして「このプロジェクトを我々がうまくまとめてやろう」と考えた瞬間に、事業部との関係性が非常に難しくなります。原則的にはサポーター役に徹することが重要だと私は思っています。
ー 具体的にはどのような取り組みで関係性を構築されているのでしょうか?
大きく3つの取り組みをしています。
1つ目は、月1回のテーマ別勉強会の開催です。ベンチャーキャピタルなどにお願いして、宇宙、生成AI、モビリティといったテーマでオンライン勉強会を開催し、面白そうだと思ってくれる人を増やしています。これによって、社内で先端技術に関心のある人のリストも把握できますし、誰に何を紹介すればいいかも分かるようになります。
2つ目は、検証用予算の確保です。特に若い社員だと興味はあるけど部門の予算を検証に使えないことが多いです。そこで我々の部門で予算を一定程度確保して「トライアル予算もあるので試してみませんか」と提案します。成功すれば担当者は評価されますし、我々としても検証が成立すると他部門に展開でき、効果のインパクトを全社に波及することができるので、関係者全員にメリットがある構造になります。
3つ目は、事業部への成功体験の提供です。「すごく評価される成果が残った」「課題に感じていたところが解決に向かって動いた」といった成功を相手にパスして、それを繰り返すことで評判を高めていく。これが最も重要な部分だと思います。
オープンイノベーションは一見「かっこいい取り組み」に映りますが、あくまで私たちはサポーターですので、その位置づけをしっかりチームのメンバーにも認識してもらうことが大事です。
「あの部門と付き合いたい」「あの部門の人と一緒に仕事がしたい」と思ってもらう関係性を事業部と構築しないと、オープンイノベーションは上手く進まないと考えています。
ー 経営層への報告体制について教えてください。
年2回、40~50枚のスライドで報告しています。報告内容は大きく3つのパートに分かれています。
まず前半部分では、投資やポートフォリオ企業の状況の全体を報告します。投資先一覧とそれぞれの現在の経営状況、業績や企業価値が上向いているのかそうでないのかが一目で見えるよう工夫しています。各投資先については1ページずつ、経営状況やPLの概略を報告するようになっています。
中盤では協業の実績を報告しています。協同で開発した製品のような具体的な成果を、ビジュアルも含めて数枚のスライドでまとめています。
最後に参考情報として、半年間でどういった企業をどの部門に紹介したかをリストで網羅的に提示します。基本的には経営層が気になるポイントをすべて資料に落とし込んで、漏れのない報告を心がけています。
ー かなり詳細な報告をされているのですね。そこまで丁寧に報告される理由は。
報告を受ける経営層が最も気にするのは、「ちゃんと管理できているのか」「いい加減な投資をしていないか」「協業を生むためにどれだけ取り組んだか」といった点です。こうした懸念に応えるため、すべての活動を数値で管理しています。3143社の情報収集、617件の事業部門への紹介、その後の採用に至ったものも含めて、すべてカウントしてリストで管理しています。
数値化することで予想外の効果も生まれました。継続のための決裁会議で、第2期の提案をした際に各事業部への貢献を数値で報告したところ、「うちの事業部は紹介件数が少ないじゃないか、もっと支援してくれ」という要望がトップから出てきたんです。
事業部門間には競争意識もありますので、「もっと連携を強化してほしい」という前向きな要請にもつながりました。これは数値で示すことで初めて生まれた反応だと思います。
何より重要なのは、評価不能な状態に陥らないことです。数値がなければ「なんとなく良い活動をしている」という曖昧な評価になってしまいます。そうなると、会社の状況が変わった際にオープンイノベーションの機能はなくてもよいという選択肢も簡単に出てきてしまう可能性があります。だからこそ、経営層や意思決定者がオープンイノベーションの活動を適切に評価できる材料を常時準備しておくことが重要なんです。
ー 今後の課題や取り組みについて教えてください。
まず、とにかくオープンイノベーション活動は長くやらないと結果が出ないと思っているので、長く続けられる努力を継続したいと思っています。
課題として感じているのは、技術トレンドの「先読み」と「現場ニーズ」のタイミングのギャップです。我々が最先端のテクノロジーやサービスを発見していち早く事業部に提案しても、その時は「必要ない」と消極的な反応を示すことがあります。しかし数年後に、経営層からその領域を強化するよう指示が出るケースがよくあります。
AIや3Dプリンティングなどがまさにそうでした。我々が数年前に一生懸命情報収集して提案していたのに受け入れられず、今になって「なぜもっと早く取り組まなかったのか」と言われてしまう。
このタイミングのギャップをどう埋めていくかが今後のチャレンジです。本来は他社よりも早く取り組むことが競争力につながるはずなのですが、組織の力学上、事業部門ではそういうわけにもいかない──ここを変えるために何をどうすればいいかは、まだこれから考える必要があります。
ー 最後に、参加者の皆様へメッセージをお願いします。
私もアドバイスする立場ではないなと思っていて、まだ目立った成功をしているとも言えないですし、まだまだやるべきことがいっぱいあると思っています。
皆様と課題を共有しながら一緒に成長できればと思いますし、皆様の取り組みもお伺いできる機会がありましたら楽しみにしております。
オープンイノベーションの実践は、時間をかけた地道な積み重ねと、社内外の信頼関係の構築によって初めて成果へとつながっていきます。戸田建設の取り組みからも、粘り強い活動と丁寧な社内連携がいかに重要であるかが浮き彫りになりました。
自社でオープンイノベーションを推進する際も、こうした成功事例から学びつつ、自社ならではの仕組みづくりを模索していくことが求められます。
ケップルは、これまで数多くの事業会社のオープンイノベーションやスタートアップ投資を支援してきた経験とノウハウを活かし、戦略設計から実行まで一貫してサポートいたします。オープンイノベーションは、正しいアプローチで取り組めば必ず成果につながります。少しでもオープンイノベーション推進にご関心をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。
【お問い合わせはこちら】
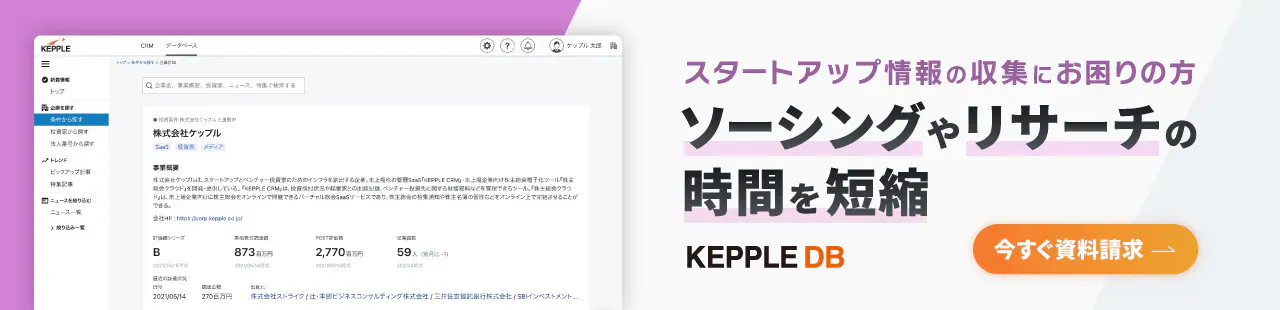
スタートアップの資金調達情報を漏れなくキャッチアップしたい方へ。
1週間分の資金調達情報を毎週お届けします。
※登録することでプライバシーポリシーに同意したものとします
※配信はいつでも停止できます